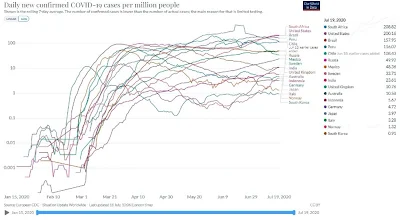|
| 沖縄県尖閣諸島 |
三流の指導者は、行き詰まると戦争に打って出る特徴がある。
周囲にイエスマンと茶坊主しかいない中国の習近平執行部。その失敗を冷ややかに待つのが李克強首相や、汪洋副首相ら共産主義青年団だ。
アジア太平洋経済協力会議(APEC)は当初、反共の連合だった。いつしか全加盟国が中国のサプライチェーンに巻き込まれ、中国批判は希釈化した。南シナ海の領海問題ではベトナム、フィリピンが強硬だが、カンボジアなど「北京の代理人」かと思われる振る舞いである。
東シナ海、南シナ海に戦雲が湧き、派手に展開する中国の軍事演習と米軍の対応を目撃すれば、ドナルド・トランプ米大統領のいう「台湾防衛」の本気度が試されることになる。沖縄県・尖閣諸島周辺での領海侵犯、接近は頻度が増した。
しかし、中国国内事情を勘案すれば、「裸の王様」はすっかり飽きられており、「習近平よ、さようなら」というムードなのだ。
第1は、全国人民代表大会(全人代)で、国内総生産(GDP)成長率の目標値が明示されず、第1四半期はマイナス6・8%と報告された。果たして、その程度で済むのか? 雇用が特に懸念され、李首相は「9億の労働者人口があり、雇用を守り、雇用機会を創造する」と記者会見した。
第2は、景気刺激策を遂行するための無謀な財政措置である。
金利の低め誘導、中小企業への融資拡大など主に企業支援政策である。新しく債務となる財政支出は合計5・5兆元(約84兆2600億円)。これは中国GDPの4・1%に相当する。
第3に、李首相の基調演説から、台湾「平和的統一」の文言が消えたことだ。
台湾総統に再選された蔡英文氏は、就任式で「(中国の唱える)一国二制度には反対」と明確なメッセージを出した。
尖閣諸島周辺や台湾海峡に、中国海軍の艦船が出没し、領空接近は日常の風景となった。日本の「2020年防衛白書」は明確に、中国の軍事的脅威を記載するようになった。
中国の富裕層は、全人代で打ち出された「香港の治安維持強化」という方向に賛同を示しつつも、ホンネでは不安視し、資産をもっと安全な場所へ移管している。
マイナスになることは分かっていても、中国は強硬路線を捨てられない。国際的に四面楚歌(そか)でも、対外活動を強硬路線で展開しなければ習政権は国内で孤立するという矛盾を抱えているからだ。
そして、すべての矛盾をそらす最後の手段が戦争である。
■宮崎正弘(みやざき・まさひろ) 評論家、ジャーナリスト。1946年、金沢市生まれ。早大中退。「日本学生新聞」編集長、貿易会社社長を経て、論壇へ。国際政治、経済の舞台裏を独自の情報で解析する評論やルポルタージュに定評があり、同時に中国ウォッチャーの第一人者として健筆を振るう。著書に『戦後支配の正体 1945-2020』(ビジネス社)、『「コロナ以後」中国は世界最終戦争を仕掛けて自滅する』(徳間書店)など多数。
当時ウェイド客員研究員は、中国の新書『中国は恐れない――国家安全保障への新脅威と戦略対応』を分析し、人民解放軍の戦略の一部として、軍人か否かを問わず国内の精神的引き締めを行なうと共に、中国の動を規制する外国勢力を牽制するものであると分析し、その他にも、人民解放軍が係ったと思われる映画と通信社の記事にも、同様の分析が成り立つことを主張しました。
中国の映画『静かなる競争』は、2013年10月に中国及び世界のネットに上がるや否や論争を呼びました。そして、その月の末までには、何の告知もなく、映画は中国のサイトからは削除されました。ただ、YouTubeでは見ることができましたが、今は削除されています。
映画は、米国が、5つの方法によって中国政府を転覆させようとしている様子を描いています。その方法とは、(1)政治的に中国を弱体化させる、(2)文化的浸透を図る、(3)思想戦をしかける、(4)諜報部隊を訓練する、及び(5)中国国内の反体制派を強化すること、です。全体としては、米国が中国を支配下に置こうとしているということを伝えたいようです。映画を見た中国国内の軍人や民間人は、侮辱された感情と怒りを持つだろう内容です。
映画の製作に人民解放軍は密接にかかわりました。具体的には、国防大学、中国社会科学院、及び、国家安全部の管轄にある現代国際関係研究院が、2013年初めに映画の製作に関与しました。これは、確かに、米国のアジア回帰に対応したものですが、より深い根本原因もあるでしょう。これだけ権威ある中国の諸機関が映画製作に携わったということは、そこで示された極端な感情が人民解放軍のタカ派に限られたものではないことを表しています。
2013年7月には、更に問題となる領土回復主義の記事が、中国新聞網のサイトに掲載されました。この記事は、「今後50年間に中国が戦わなければならない6つの戦争」という題名で、人民解放軍の一部に見られる超国粋主義の態度を示しています。しかし、このような記事が中国国営通信社に掲載されるという事実から、これが指導部で認められた考えであることが想像出来ます。
6つの「不可避な」戦争は、時系列で示されています。(1)台湾統一戦争(2020-2025年)、(2)南シナ海の様々な諸島の領土回復戦争(2025-2030年)、(3)チベット南部の領土回復戦争(2035-2040年)、(4)釣魚島及び琉球諸島回復戦争(2040-2045年)、(5)外蒙古統一戦争(2045-2050年)、(6)ロシアに奪取された領土の回復戦争(2055-2060年)です。
台湾に関しては、中国は、武力行使の手段を放棄したことはなく、具体的時期が示されたこともそれまではありません。偶然でしょうが、丁度この頃、台湾軍が、中国は2020年までに台湾を併合する軍事的能力を有するだろう、と発表したばかりでした。
尖閣諸島に対する中国の領有権の主張は、最近よく報道されるので、その状況が戦争に発展するのにさほどの想像は必要としないでしょう。今年は、現在までにすでに100日以上も中国の海警局の艦艇が、尖閣付近に出没しています。
また、モンゴルが清王朝から継承した土地に関しても、中国は領有権を主張しています。ロシアの極東地域についても同様で、多くの中国人は、そこはロシアが不当に占拠したものだと思っています。
本年2020年は、中国の二つの100年計画の一つ「小康社会の全面的実現」目標の期限である建党100周年の2021年より一年前であり、もしこの時点でいずれかの戦争を行い、それに勝利すれば、習近平政権にとっては長期独裁を全党および人民に納得させるだけの効果を持つ歴史的偉業となります。
周囲にイエスマンと茶坊主しかいない中国の習近平執行部。その失敗を冷ややかに待つのが李克強首相や、汪洋副首相ら共産主義青年団だ。
アジア太平洋経済協力会議(APEC)は当初、反共の連合だった。いつしか全加盟国が中国のサプライチェーンに巻き込まれ、中国批判は希釈化した。南シナ海の領海問題ではベトナム、フィリピンが強硬だが、カンボジアなど「北京の代理人」かと思われる振る舞いである。
東シナ海、南シナ海に戦雲が湧き、派手に展開する中国の軍事演習と米軍の対応を目撃すれば、ドナルド・トランプ米大統領のいう「台湾防衛」の本気度が試されることになる。沖縄県・尖閣諸島周辺での領海侵犯、接近は頻度が増した。
しかし、中国国内事情を勘案すれば、「裸の王様」はすっかり飽きられており、「習近平よ、さようなら」というムードなのだ。
第1は、全国人民代表大会(全人代)で、国内総生産(GDP)成長率の目標値が明示されず、第1四半期はマイナス6・8%と報告された。果たして、その程度で済むのか? 雇用が特に懸念され、李首相は「9億の労働者人口があり、雇用を守り、雇用機会を創造する」と記者会見した。
第2は、景気刺激策を遂行するための無謀な財政措置である。
金利の低め誘導、中小企業への融資拡大など主に企業支援政策である。新しく債務となる財政支出は合計5・5兆元(約84兆2600億円)。これは中国GDPの4・1%に相当する。
台湾総統に再選された蔡英文氏は、就任式で「(中国の唱える)一国二制度には反対」と明確なメッセージを出した。
尖閣諸島周辺や台湾海峡に、中国海軍の艦船が出没し、領空接近は日常の風景となった。日本の「2020年防衛白書」は明確に、中国の軍事的脅威を記載するようになった。
中国の富裕層は、全人代で打ち出された「香港の治安維持強化」という方向に賛同を示しつつも、ホンネでは不安視し、資産をもっと安全な場所へ移管している。
マイナスになることは分かっていても、中国は強硬路線を捨てられない。国際的に四面楚歌(そか)でも、対外活動を強硬路線で展開しなければ習政権は国内で孤立するという矛盾を抱えているからだ。
そして、すべての矛盾をそらす最後の手段が戦争である。
■宮崎正弘(みやざき・まさひろ) 評論家、ジャーナリスト。1946年、金沢市生まれ。早大中退。「日本学生新聞」編集長、貿易会社社長を経て、論壇へ。国際政治、経済の舞台裏を独自の情報で解析する評論やルポルタージュに定評があり、同時に中国ウォッチャーの第一人者として健筆を振るう。著書に『戦後支配の正体 1945-2020』(ビジネス社)、『「コロナ以後」中国は世界最終戦争を仕掛けて自滅する』(徳間書店)など多数。
【私の論評】中国は総力戦はしないが、6つの不可避な戦争のいずれかに挑戦する可能性は十分ある!(◎_◎;)
中国ウォッチャーとして有名な、上の宮崎正弘氏の記事では、矛盾を逸らす最後の手段としての戦争があり得ることを主張しています。
戦争というと、まず頭に浮かぶのは、台湾を武力統一することです。それに、尖閣諸島の奪取もあり得ます。これらは、日本人ならすぐに思い浮かぶことです。他には、どのような戦争があり得るのでしょうか。
昨日このブログでは、トゥキディディスの罠に嵌って、米中両国が総力戦に入ることはないであろうことと、その根拠も述べました。その上で、総力戦はないものの局地戦はあり得ることを主張しました。その事例として、米軍による南シナ海の中国軍基地への攻撃を挙げました。
本日は、その続きとして、中国による局地戦としては、どのようなものが考えられるのかを掲載します。
これに対するヒントとなるような内容が、2013年11月26日豪州戦略政策研究所(ASPI)のブログ・サイトThe Strategistに掲載されていました。豪州国立大学(ANU)のウェイド客員研究員が、中国がメディアを通して、反米感情を煽ったり、領土拡張を訴えたりしている現状を紹介して、警告を発しました。
中国の映画『静かなる競争』は、2013年10月に中国及び世界のネットに上がるや否や論争を呼びました。そして、その月の末までには、何の告知もなく、映画は中国のサイトからは削除されました。ただ、YouTubeでは見ることができましたが、今は削除されています。
映画は、米国が、5つの方法によって中国政府を転覆させようとしている様子を描いています。その方法とは、(1)政治的に中国を弱体化させる、(2)文化的浸透を図る、(3)思想戦をしかける、(4)諜報部隊を訓練する、及び(5)中国国内の反体制派を強化すること、です。全体としては、米国が中国を支配下に置こうとしているということを伝えたいようです。映画を見た中国国内の軍人や民間人は、侮辱された感情と怒りを持つだろう内容です。
映画の製作に人民解放軍は密接にかかわりました。具体的には、国防大学、中国社会科学院、及び、国家安全部の管轄にある現代国際関係研究院が、2013年初めに映画の製作に関与しました。これは、確かに、米国のアジア回帰に対応したものですが、より深い根本原因もあるでしょう。これだけ権威ある中国の諸機関が映画製作に携わったということは、そこで示された極端な感情が人民解放軍のタカ派に限られたものではないことを表しています。
2013年7月には、更に問題となる領土回復主義の記事が、中国新聞網のサイトに掲載されました。この記事は、「今後50年間に中国が戦わなければならない6つの戦争」という題名で、人民解放軍の一部に見られる超国粋主義の態度を示しています。しかし、このような記事が中国国営通信社に掲載されるという事実から、これが指導部で認められた考えであることが想像出来ます。
台湾に関しては、中国は、武力行使の手段を放棄したことはなく、具体的時期が示されたこともそれまではありません。偶然でしょうが、丁度この頃、台湾軍が、中国は2020年までに台湾を併合する軍事的能力を有するだろう、と発表したばかりでした。
南シナ海に関しては、現在のいざこざが戦争に発展することは想像に難くないです。3つ目の中国によるインドのArunachal Pradesh州への領有権の主張は、何十年も中印関係の棘でしたが、中国がヒマラヤのチベット文化圏のどこまでを勢力圏として主張しているかは、今だ明らかにされていません。今年の6月15日夜、ヒマラヤ高地のギャルワン渓谷で中印が衝突。報道では両国で数十人の死者が出たもようです。
尖閣諸島に対する中国の領有権の主張は、最近よく報道されるので、その状況が戦争に発展するのにさほどの想像は必要としないでしょう。今年は、現在までにすでに100日以上も中国の海警局の艦艇が、尖閣付近に出没しています。
また、モンゴルが清王朝から継承した土地に関しても、中国は領有権を主張しています。ロシアの極東地域についても同様で、多くの中国人は、そこはロシアが不当に占拠したものだと思っています。
上記の戦争は、現在の中国の政策で裏付けされたものでもなければ、極端な超国粋主義者の見解にすぎないかもしれないです。しかし、戦争によって領土を回復しなければならないという主張は、長い間中国で言われてきたことです。
中国(中華民国)政府公認の1938年「中国の屈辱」地図は、上記記事が主張する領土と驚くほど一致しています。この地図の中国が「失った」領土には、ロシア極東、琉球諸島、台湾及び南シナ海のみならず、韓国、ヴェトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、マレー半島とシンガポール、ネパール、パキスタンの一部及び中央アジアの殆どが含まれています。
 |
| 「中国の屈辱」地図 |
中国の主張する領土が、今日の中国の国境を超えて70年以上前に遡ることや、中国の超国粋主義者の言い分を読むにつけ、我々は、これらの地域に住む人々が、恐怖を感じたり危険に晒されたりすることがないようにしなければならないだろう、と論じています。
中国の戦略は、中長期的です。上記の論説で紹介された記事のように、50年間で6つも戦争をしかけては中国ももたないと思いますが、中国人民解放軍は、ハードな軍事戦争のみならず、「三戦」(心理戦、情報戦、法律戦)と呼ばれるソフトな戦争もしかけます。更に、今日では、経済や文化も重要な手段となり、人海戦術も活用しています。
5カ年計画、10カ年計画は、中国共産党の一政権の期間であり、中国にとっての中期、長期は、50年、100年の戦略計画となります。
欧米や日本等の民主主義国は、単年度予算かつ政権も4年位の任期で(最近まで日本の政権は1年位でした)、中長期は、5~10年の計画となります。
ただ、 50年、100年の戦略計画は、たとえそれが国家による計画といえども、あまりに長期です。そもそも、そのようなスパンでは、計画当初の中共幹部のほとんどが、亡くなっているか、引退しているはずです。それに、最初の想定から、世界情勢や技術水準などあらゆる想定が異なるものなり、ほとんど無意味な計画になるでしょう。
中国の戦略は、中長期的です。上記の論説で紹介された記事のように、50年間で6つも戦争をしかけては中国ももたないと思いますが、中国人民解放軍は、ハードな軍事戦争のみならず、「三戦」(心理戦、情報戦、法律戦)と呼ばれるソフトな戦争もしかけます。更に、今日では、経済や文化も重要な手段となり、人海戦術も活用しています。
5カ年計画、10カ年計画は、中国共産党の一政権の期間であり、中国にとっての中期、長期は、50年、100年の戦略計画となります。
欧米や日本等の民主主義国は、単年度予算かつ政権も4年位の任期で(最近まで日本の政権は1年位でした)、中長期は、5~10年の計画となります。
ただ、 50年、100年の戦略計画は、たとえそれが国家による計画といえども、あまりに長期です。そもそも、そのようなスパンでは、計画当初の中共幹部のほとんどが、亡くなっているか、引退しているはずです。それに、最初の想定から、世界情勢や技術水準などあらゆる想定が異なるものなり、ほとんど無意味な計画になるでしょう。
現実的には、やはり5年〜10年の計画でしょう。このブログでは、中国海軍のロードマップを紹介したことがあります。それによれば、中国海軍は既に尖閣列島を含む第一列島線を傘下に収め、今年は第二列島線を我がものに収めることになっています。ご存知のように、尖閣諸島すら奪取できない今日、これはもうほとんど絵に描いた餅にすぎません。
私は、習近平自身もこれらの計画が計画通りに進むなどとは思っていないと思います。そんなことより、我々が危惧すべきは、プーチンによるクリミア統合のようなことが、習近平によってなされる可能性です。
2018年ロシアの大統領選挙のとき、プーチンの支持率かなり高いものでした。その4年前、ウクライナ南部のクリミアを併合したことに対する欧米からの経済制裁。そして主力の輸出品である原油の価格低迷。ロシアは当時も、厳しい経済状況を抜け出せずにいました。
国民の可処分所得は4年連続で落ち込み、最低生活費よりも低い所得で生活している人は、この4年間で400万人以上増加しました。国民の生活実感はなかなか改善されないのが現実でした。
それにもかかわらず、当時、プーチン大統領の支持率は80%台で推移。モスクワでは2017年12月、プーチン大統領を題材にした絵画や彫刻などを集めた美術展覧会「スーパープーチン」も開かれるなど、人気にかげりは見られませんでした。2018年の大統領選挙でプーチンは、通算4期目の当選を果たしました。
それにもかかわらず、当時、プーチン大統領の支持率は80%台で推移。モスクワでは2017年12月、プーチン大統領を題材にした絵画や彫刻などを集めた美術展覧会「スーパープーチン」も開かれるなど、人気にかげりは見られませんでした。2018年の大統領選挙でプーチンは、通算4期目の当選を果たしました。
 |
| 2017年12月開催された美術展覧会「スーパープーチン」 |
それは、やはり戦争を起こし、それに勝利したことが大きいでしょう。戦争は、多くの国民に愛国心を燃え上がらせる一つの手段でもあります。この戦争がなければ、あるいはこの戦争に負けていれば、プーチンは今頃引退していたかもしれません。
私は、このようなことを習近平も考えるの可能性は十分あると思います。このブログでも何度か紹介されていただいたように、中国は自国の都合で動く国であり、そもそも外交などあまり重視していません。
本来戦争は、外交手段を尽くしても解決できない他国との争いを解決するための手段の一つに過ぎないのですが、習近平は対外活動を強硬路線の最強の手段として、戦争を選ぶ可能性は十分あります。そうして、その目的は、習近平自身の統治の正統性を強化することにあります。
そもそも、習近平は、建国の父毛沢東や、経済改革を実現した鄧小平などのような大きな実績はありません。だから、統治の正統性は、どうしても弱いところがあります。
中国では、ロシアのように選挙がありませんが、だからこそ、誰の目にも明らに統治の正当性を主張し、特に共産党の中で自己の正当性を主張する必要があります。
上に掲載した六つの戦争のうち、いずれかの戦争を行い、勝利すれば、習近平の統治の正統性は飛躍的に高まり、当面大きな権力闘争などしなくてもすむようになります。
ですから、今年中にもいずれかで局地戦争が起こる可能性は、十分にあります。習近平としても、大きな冒険はしたくないので、米国と直接対決せざるを得なくなるような戦争はしないと思います。
 |
| 中国とソ連は1929年と1969年に国境紛争をしており、1969年の時は核戦争一歩手前まで行った |
台湾統一戦争、南シナ海の領土回復戦争、尖閣諸島奪取などは、米国が直接絡みます。もしこれらが、攻撃されれば、米国はすぐに反撃に出る可能性があります。ロシアに奪取された領土の回復戦争もやりたくはないでしょう。
中露は互いに友情は感じていないかもしれませんが、それにしても、国連などでは、中国に賛成する数少ない国の一つでもあります。それに過去には、中ソ国境紛争という苦い経験もあります。
そうなると、チベット南部のインドからの領土回復戦争あたりが手頃でやりやすいかもしれません。
これは、インドにとっては脅威ですが、中国に対抗する勢力にとっては、一つのチャンスかもしれません。これを完膚なきまでに、打ち負かせば、習近平の統治の正統性は地に落ちることになり、失脚する可能性もあります。
【関連記事】