中国の景気減速が米FRBのインフレ対策の追い風に
中国経済は 2023 年に予想以上に減速している。成長予測は引き下げられ、インフレ率は低下している。
中国の景気減速は世界経済と市場に悪影響を及ぼしている。 一次産品の価格は下落しており、商品の需要は減少している。 現状では、世界的にインフレの軌道修正が課題となっている。
中国経済の減速は、米国連邦準備制度理事会とそのジェローム・パウエル議長にとって救いとなっている。
 |
| FRBジェローム・パウエル議長 |
中国経済の減速は、近年政策決定に欠陥があった FRBに対する積極的な利上げ継続への圧力を軽減しています。
中国ではデフレの兆候が見られ、消費者物価と生産者物価が多くの分野で下落している。 中国の内需は著しく減速している。 中国の輸出に対する外需も急減した。
中国の景気減速は、今年の力強い中国の成長を期待していた米国および世界経済にとって悪いニュースである。
しかし、中国は依然として金融政策と財政政策を通じて経済を刺激する可能性がある。
中国は、債務水準の削減と通貨安の回避に努めるため、大規模な景気刺激策の実施を躊躇する可能性がある。 積極的な刺激策は、中国の不動産セクターでさらなる問題を引き起こし、米国との緊張を高める可能性がある。
今のところ、中国経済の減速により、米国を含む世界全体のインフレ圧力が低下している。しかし、中国の政策担当者が成長刺激を決定すれば、状況は変わる可能性がある。
これは、
元記事の要約です。詳細を知りたい方は、
元記事をご覧ください。
【私の論評】中国長期経済停滞で、世界の「長期需要不足」は終焉?米FRBのインフレ対策の追い風はその前兆か(゚д゚)!
上の記事では、中国経済の減速により、近年政策決定に欠陥があったFRBに対する積極的な利上げ継続への圧力が弱まり、米FRBの反金融政策の追い風になったと主張しています。
私は、この主張に賛成します。 中国経済の減速は確かにFRBにある程度の安心感をもたらし、インフレ抑制の取り組みを助けているようです。
FRBは近年、2019年の過度な利下げや物価上昇への対応の遅れなど、いくつかの重大な政策ミスを犯していました。 FRBは巻き返しを図る必要があり、積極的な利上げは米国経済を過度に減速させるリスクがあります。
 |
| 米国の高インフレは収まりつつある |
中国からの需要鈍化もあり、世界的にインフレ圧力が緩和しているため、FRBはより柔軟性を持ち、以前の予想ほど急速に高い利上げをする必要がなくなりました。 これは、FRBが引き締めすぎて米国の成長に深刻なダメージを与えるリスクを軽減するのに役立つでしょう。
一次産品価格の下落、米国製品に対する需要の減少、中国経済の減速による生産者コストの低下はすべて、米国のインフレを最近の高水準から引き下げるのに役立っています。 このディスインフレ傾向はFRBが物価安定を達成するのに役立っています。
中国経済が依然として好景気であったとすれば、世界的なインフレ圧力は依然として高止まりする可能性が高く、FRBはインフレ率を目標に戻すためにより積極的な行動をとらざるを得なくなるでしょう。
中国経済の減速は米国や世界経済にとって理想的ではないですが、インフレ抑制という狭い目標にとってはFRBに短期的な利益をもたらすことになります。 FRBがインフレ抑制に向けて取り組むべき道はまだ残っていますが、中国経済の苦境により、当面はFRBの仕事が少なくとも少しは楽になりつつあるのは間違いないようです。
中国の政策担当者が成長刺激を決定すれば、状況は変わる可能性もあります。ただ、従来からこのブログで述べているように、中国は国際金融のトリレンマにより独立した金融政策ができない状況にあるため、中国はしばらく過去のようには成長刺激策をとれない可能性が高いと思われます。
中国が独立した金融政策を実施できなければ、政府は従来のように成長を刺激することは当面困難になるでしょう。 これは中国経済の減速の長期化につながり、世界の成長に悪影響を与える可能性があります。
国際金融のトリレンマでは、国は次の 3 つの政策を同時に実施することはできないとされています。できるのは、せいぜい2つです。
中国では固定為替レートが採用されており、人民元の価値は米ドルに固定されています。 このため、中国政府が中国の輸出品を安くし、成長を促進する人民元切り下げを行うことが困難になっています。量的緩和も難しいです。
また、中国は資本移動が比較的自由であり、これはお金が比較的簡単に国に出入りできることを意味します。 このため、中国政府が成長を促す金利引き上げも困難になっています。
その結果、中国は困難な状況に陥っています。 政府が従来の手段で成長を刺激しようとすると、人民元の切り下げや資本規制につながる可能性が高いです。 これらの措置はいずれも中国経済と世界経済に悪影響を与えるでしょう。
中国が成長を刺激する最善の方法は、構造改革に注力することです。 これは、経済における国家の役割を軽減し、金融セクターの効率を改善し、企業にとってより平等な競争条件を作り出すことを意味します。 これらの改革の実施には時間がかかりますが、長期的にはより持続可能となるでしょう。
一方、米国を含む多くの国は、中国経済の減速を前提に困難な状況を乗り切ることを余儀なくされるでしょう。 世界経済に大きな打撃を与えないよう、政府と中央銀行間の慎重な調整が必要となります。
 |
| 中国経済の減速 |
ただ、習近平は、習近平が変動相場制への移行などの構造改革に乗り出すことに消極的である理由はいくつか考えられます。
政治的考慮事項。 経済を管理する国家の力を信じている共産主義指導者です。 同氏はまた、構造改革が不安定や社会不安につながることを懸念してます。 その結果、同氏が近い将来に大規模な構造改革に着手する可能性は低いです。
さらに、中国経済は依然として比較的健全なペースで成長しているため、直ちに大規模な改革が必要というわけでありません。 実際、一部の経済学者は、構造改革は短期的には実際に中国経済に悪影響を与える可能性があると主張しています。
中国は米国やその他の国から経済改革を求める圧力の増大に直面しています。 しかし、習近平は、そうすれば世界における中国の立場が弱まると信じているため、これらの国々に大きな譲歩をする可能性は低いです。
結局のところ、構造改革に着手するかどうかの決定は政治的なものです。 習近平氏は決定を下す前に、改革の経済的、政治的コストと利益を比較検討する必要があるでしょう。
いずれにせよ、中国経済は、ここしばらくは、低迷を続けるのは間違いないです。いずれの国も今後は、これを前提として製剤政策を実行する必要があります。
ただ、長期にわたる中国経済の減速は、デメリットばかりではありません。
1990年代末から顕在化し始めた中国に代表される新興諸国の貯蓄過剰が、世界全体のマクロ・バランスを大きく変えました。各国経済のマクロ・バランスにおける「貯蓄過剰」とは、国内需要に対する供給の過剰を意味します。実際、中国などにおいてはこれまで、生産や所得の高い伸びに国内需要の伸びが追いつかないために、結果としてより多くの貯蓄が経常収支黒字となって海外に流出してきました。このように、供給側の制約が世界的にますます緩くなってくれば、世界需要がよほど急速に拡大しない限り、供給の天井には達しません。供給制約の現れとしての高インフレや高金利が近年の先進諸国ではほとんど生じなくなったのは、そのためです。この「長期需要不足」の世界は、ローレンス・サマーズが「長期停滞論」で描き出した世界にきわめて近いです。その世界では、財政拡張や金融緩和を相当に大胆に行っても、景気過熱やインフレは起きにくいのです。
 |
| ローレンス・サマーズ |
というよりもむしろ、財政や金融の支えがない限り、十分な経済成長を維持することができず、ひとたびその支えを外してしまえば、経済はたちまち需要不足による「停滞」に陥ってしまうのです。それが、供給の天井が低かった古い時代には必要とされていた緊縮が現在はむしろ災いとなり、逆に、その担い手が右派であれ左派であれ、世界各国で反緊縮が必要とされる理由になってきました。
ローレンス・サマーズの長期停滞理論は、世界経済が長期的な低成長時代に直面していると主張するマクロ経済理論です。 この理論は、世界経済が貯蓄を増やし、投資を減らしている原因は数多くあるという考えに基づいています。 これらの要因には次のものが含まれます。
先進国における人口の高齢化。 人は年齢を重ねるにつれて、より多くの貯蓄をし、より少ない支出をする傾向があります。 これは、彼らが老後のために資産を蓄積しており、新たな借金を負う可能性が低いためです。
不平等の拡大。 ここ数十年で不平等が拡大するにつれ、中産階級から富裕層への収入の移動が起きているとされています。 富裕層は中産階級よりも多く貯蓄する傾向があるため、この変化が世界的な貯蓄の増加につながっています。
投資機会の減少。 ここ数十年で世界経済の統合が進み、先進国における投資機会の減少につながっています。 これは、先進国では新興国に比べて高い投資収益率を得る機会が少ないためです。
これらの要因により、世界的な貯蓄過剰、つまり投資よりも貯蓄が多い状況が生じています。 この供給過剰により金利が低く抑えられ、経済成長の刺激が困難になっているのです。
サマーズの理論は物議を醸していますが、近年ではある程度の支持を得ています。 2016年、IMFは世界経済が長期停滞の時期に直面していると主張する報告書を発表しました。 報告書は政府に対し、インフラ投資や減税など経済成長を刺激する措置を講じるよう求めましたた。
サマーズの理論が正しいかどうかを判断するのはまだ時期尚早です。 しかし、今後数年間に世界経済が直面する課題を理解するのに役立つ可能性があるため、これは検討する価値のある理論といえます。そうして、中国の経済の停滞がある程度続けば、この理論の妥当性をみる、機会が訪れるかもしれません。それは、そう遠くない時期に実現するかもしれません。
中国の経済の停滞が続けば、「長期需要不足」の時代は終わるのではないでしょうか。そうなれば、今後は、財政拡張や金融緩和を相当大胆に行えば、従来のように、景気加熱やインフレが起きやすくなることを意味します。
中国経済の減速は、世界の各国のマクロ経済の状況が一昔前に戻ることを意味するかもしれません。そうなれば、「長期需要不足」、「長期停滞」は過去のものとなり、多くの国々で、経済政策が実施しやすくなるかもしれません。米国での中国の景気減速が米FRBのインフレ対策の追い風となっている事実は、その魁なのかもしれません。
現在まで、世界の各国のマクロ経済状況は、緊縮財政を行えば、経済が後退する一方で、金融緩和や積極財政をするかしないかというのが常道となりつつあったのが(これを全く認識していないのが財務省と旧タイプの日銀官僚)、一昔前のように、経済が落ち込めば、金融緩和をし、積極財政を行い、景気が加熱すれば、金融引締をし、緊縮財政をするというように、比較的簡単にコントロールできるようになるのではないでしょうか。
考えてみると、一人あたりのGDPがいまだかなり低いにもかかわらず、中国の貯蓄過剰という状況が異常だったのであり、中国経済がしばらく停滞を続ければ、世界経済はまた元にもどることになるかもしれません。
今後中国は、国内で貯蓄過剰が起きないように、国民の所得をあげ購買力の向上を目指し、内需を拡大することによって、発展することもできるのではないかと思います。それをしなかったからこそ、貯蓄過剰になったのです。
それとともに、中国は独立した金融政策を取り戻すために、変動相場制に移行したり、国際標準の中央銀行の独立性を確保したりして、金融システムの透明性や改革を図るべきです。そうして、民主化、政治と経済の分離、法治国家化もすすめるべきです。
何のことはないです。今まで世界は中国の歪な経済構造に翻弄されてきたのであり、それが中国の長期経済の停滞によって是正される方向に動き出したのかもしれません。
ただ、先に述べたような方向性で、中国が国内の経済改革を実行すれば、良いですが、中国が改革を実行しなければ、経済の停滞は長く続き、最終的に毛沢東時代の水準に戻ることになるかもしれません。
ただ、中国の長期経済停滞が続けば、先進国などは一時的には、その悪影響を受けるかもしれませんが、「長期需要不足」の状況が解消され、経済運営は実施しやすくなるでしょう。ただ、以上で述べたことは、様々な状況に左右されることが予想され、その通りになるとは限りません。
ただ、米国で中国の経済の減速が、インフレ対策の追い風になっているように、中国の経済の減速は悪いことばかりではなさそうです。
日本を含む先進国は、良い方向に向くように一致協力し、世界経済の秩序を取り戻すとともに、中国に体制の転換を促すべきです。
【関連記事】
世界が反緊縮を必要とする理由―【私の論評】日本の左派・左翼は韓国で枝野経済理論が実行され大失敗した事実を真摯に受け止めよ(゚д゚)!
「多臓器不全」に陥った中国経済―【私の論評】何度でも言う!中国経済の低調の真の要因は、国際金融のトリレンマ(゚д゚)!
中国が東南アジアから撤退開始、経済問題に直面し―【私の論評】中国は、アフリカ、ラテンアメリカ、中央アジアでも撤退しつつある(゚д゚)!
中国、地方政府の「隠れ債務」明らかにする全国調査開始-関係者―【私の論評】LGFV問題は、一筋縄ではいかない、中国こそ抜本的構造改革が必須(゚д゚)!
中国の「地方政府債務」再考―【私の論評】もう一つの中国の大問題、国際金融のトリレンマを克服すれば、中国の改革が始まるかもしれない(゚д゚)!

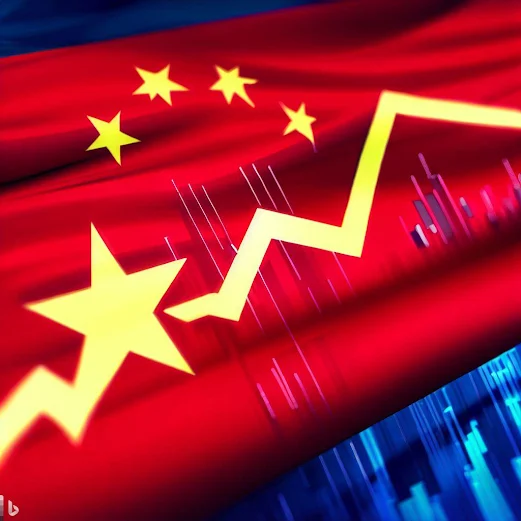



















.jpeg)
.jpeg)
_63.jpg)
.jpeg)











