まとめ
- トランプ大統領は2025年7月7日、日本に25%の関税を課す書簡を石破総理大臣に送り、貿易赤字是正と米国内製造促進を狙う。
- 日本の参院選(7月20日)は交渉に影響を与え、米国財務長官が選挙を「日本の制約」と指摘。
- 自民党内の農業保護派は農産物譲歩に反対し、参院選敗北で主導権を握れば交渉が難航する。
- 「自由で開かれたインド太平洋戦略本部」が主導すれば、自由貿易を推進し、米国に外交的対抗を試みる。
- 参院選結果と自民党内の力学が交渉の行方を左右し、日本は日米同盟と国内バランスの間で試される。
トランプの関税通知と日本の動向
 |
| 記者会見で、トランプ米大統領から石破茂首相への関税に関する書簡を示すレビット報道官 |
2025年7月7日、トランプ米大統領は日本の石破茂首相に書簡を送り、8月1日から日本製品に25%の関税を課すと宣言した。この書簡は、米国が抱える対日貿易赤字を叩き潰し、米国内の製造業を復活させるための強烈な一撃だ。書簡はTruth Socialで公開され、韓国の李在明大統領にもほぼ同じ内容が送られた。以下はその全文だ。(日本語訳はこの記事一番最後「続きを読む」に掲載します)
Letter to Prime Minister Shigeru Ishiba of Japan
Dear Prime Minister Ishiba,
For many years, the United States has experienced a long-term, and very persistent, Trade Deficit with Japan. Starting on August 1, 2025, we will charge Japan a Tariff of only 25% on any and all Japanese products sent into the United States, separate from all Sectoral Tariffs. Goods transshipped to evade a higher Tariff will be subject to that higher Tariff. If for any reason you decide to raise your Tariffs, then, whatever the number you choose to raise them by, will be added onto the 25% that we charge. There will be no Tariff if Japan, or companies within your Country, decide to build or manufacture product within the United States and, in fact, we will do everything possible to get approvals quickly, professionally, and routinely – In other words, in a matter of weeks.
We look forward to working with you as a Trading Partner for many years to come. If you wish to open your heretofore closed Trading Markets to the United States, and eliminate your Tariff, and Non Tariff, Policies and Trade Barriers, we will, perhaps, consider an adjustment to this letter. Please understand this 25% number is far less than what is needed to eliminate the Trade Deficit disparity we have with your Country. These Tariffs may be modified, upward or downward, depending on our relationship with your Country. You will never be disappointed with The United States of America.
Sincerely,
Donald J. Trump
President of the United States
この書簡は、米国の2024年対日貿易赤字(約685億ドル)を背景にしている。トランプは「America First」を掲げ、米国内の雇用と産業を守るため、関税を武器に日本に圧力をかける。書簡の言葉は直接的で、まるでビジネスの取引を持ちかけるような調子だ。「25%は控えめだ」と言いながら、報復関税にはさらに上乗せすると警告し、日本に市場開放や米国での工場建設を迫る。「数週間で承認する」と約束する一方、日本の市場を「閉鎖的」と批判する強烈な言葉も飛び出す。最後の「アメリカに失望することはない」という一文は、米国の力を誇示し、国内の支持者を鼓舞するパフォーマンスだ。
経済的には、この関税は日本の対米輸出(2024年で約1,480億ドル)に大打撃を与える。自動車や電子機器の価格が上がり、企業は利益を失うだろう。米国での工場建設を促す狙いはあるが、そんなものは一朝一夕にできるものではない。米国側でも、物価上昇や日本の報復関税(例えば米国の農産物に対する関税)のリスクがちらつく。政治的には、日米同盟にひびが入る危険があり、日本は交渉、報復、WTO提訴の三択を迫られる。だが、同盟の重みを考えると、慎重な対応を選ぶだろう。書簡の前提である「貿易赤字は悪」「関税で解決できる」という論理には、経済学者から疑問の声が上がる。サプライチェーンの混乱や国際貿易の停滞を招くリスクも見逃せない。
参院選と日本の交渉姿勢
2025年7月20日、日本の参院選が迫る。この選挙は日米貿易交渉に影を落とす。米国財務長官スコット・ベッセントは「選挙が日本の交渉を縛っている」と語り、トランプ政権が日本の国内政治を交渉の障害と見ていることを示した(出典:
NHK WORLD-JAPAN News)。自民党の支持率は低下し、東京都議選での敗北が響く。農業界は自民党の強力な支持基盤だ。米国との交渉で農産物の市場を開けば、有権者の反発は避けられない。石破首相は板挟みだ。
自民党内部では、農業保護を主張する勢力が強い。森山裕委員長の「食料安全保障強化本部」は、米国からの米の輸入拡大に反対する決議を出し、小野寺五典政策調査会長も国内産業を守る必要性を訴える(出典:
The Japan News、
The Japan News)。もし参院選で自民党が敗れ、石破政権が弱体化すれば、農業保護派が交渉の主導権を握る可能性がある。そうなれば、農産物に関する譲歩はさらに難しくなる。
食料安全保障強化本部で挨拶する森山裕自民幹事長
一方で、「自由で開かれたインド太平洋戦略本部」(FOIP本部)が別の道を提示する。麻生太郎最高顧問が本部長を務め、高市早苗や茂木敏充ら約60人の議員が参加するこの本部は、2025年5月14日に再始動し、自由貿易と地域の安定を掲げる(出典:
自民党、
NHK)。FOIP本部が主導権を握れば、自由貿易を推し進め、トランプの関税に外交的な反撃を試みるだろう。
CPTPPやRCEPといった多国間貿易枠組みを強調し、米国に自由貿易の価値を訴える可能性がある。だが、国内の農業保護派との対立は避けられない。麻生はトランプとの過去の対話経験を生かし、強気な交渉を展開するかもしれないが、農業界の反発を抑えるため、農業分野の譲歩は最小限にとどめる巧みなバランスを取るだろう。
自民党内の力学と交渉の行方
自民党の派閥は政治資金スキャンダルで解散したが、影響力は消えていない。安倍派、森山派、岸田派、二階派が名目上解散しても、非公式なネットワークは生きている(出典:
The Mainichi)。農業保護派の森山や小野寺は、農業界の声を背に強硬な姿勢を崩さない。対して、FOIP本部は自由貿易と国際協力を重視し、日米同盟を地域戦略の基盤と見る。参院選の結果がこの力学を左右する。自民党が敗北し、農業保護派が勢いづいた場合、交渉は硬直する。一方、FOIP本部が主導権を握れば、自由貿易を軸にした柔軟な交渉が期待できる。
.jpg) |
自民「自由で開かれたインド太平洋戦略本部」の初会合で挨拶する麻生最高顧問(5月14日、党本部)
|
|













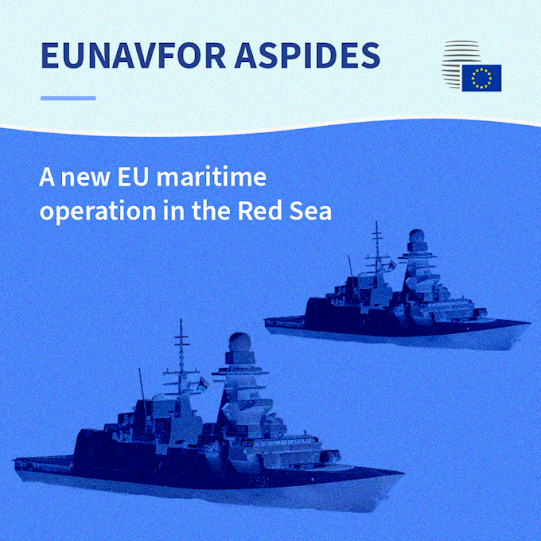




.jpg)



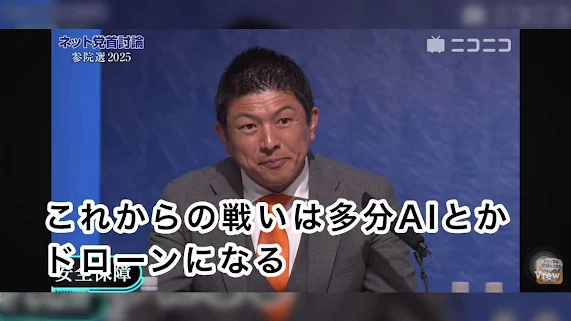




.jpg)







