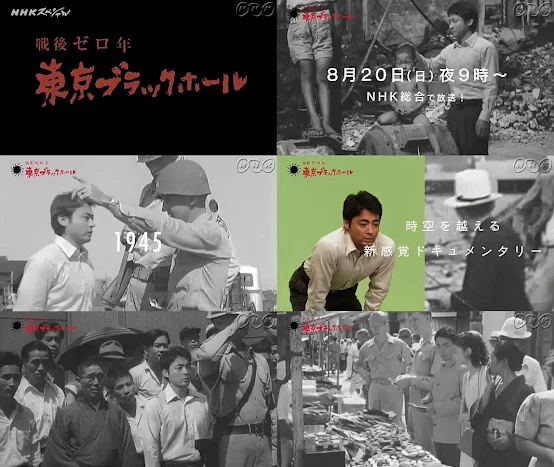◆
岡崎研究所
6月14日、ガスプロムはノルド・ストリーム経由のドイツ向けガスの供給を40%削減すると発表した(翌15日にはこれを60%に拡大した)。その理由としてパイプラインの部品の定期修繕がカナダにあるシーメンスの工場で行われているが、それがカナダ政府の対ロシア制裁によって再納入出来なくなっているとの事情をあげているという。
しかし、その説明を鵜呑みにする向きはない。イタリアのドラギ首相が言うように、その説明は嘘であり、「小麦が政治的に使われているのと同様、これはガスの政治的利用である」に違いない。
その決定の背景には、エネルギー輸出が減っても、価格の上昇がこれを補って余りあるとの計算が働いたことがあるに違いない――ウクライナ侵攻以降100日のロシアのエネルギー輸出は930億ユーロで、2021年の輸出額の約40%を100日で稼いだことになるとの試算がある。
また、プーチン大統領が西側の制裁を乗り切れると信ずるに至ったこと(その判断の当否は別として)があるかも知れない。6月17日、サンクトペテルブルグの国際経済フォーラムで演説した同大統領は西側の制裁を「常軌を逸し(insane)」「狂気じみた(crazy)」ものと呼び、西側はロシア経済を暴力的に崩壊させることを予想したが、そうはならなかった、ロシア経済は正常化する、「ロシアに対する経済的電撃戦は最初から失敗する運命にあったのだ」と述べた。
欧州ではエネルギーと食料の価格が高騰し、5月のインフレ率が8.1%と高い水準を維持する状況にあって、6月9日、欧州中銀は7月に量的緩和政策を終了し政策金利を引き上げることを発表している。
これが債権市場の動揺を招き、イタリア国債の利回りは急上昇した。10年物国債の利回り(年初は1%)は急上昇して一時4%を超えたが(目下3.7%程度)、ユーロ圏の安定を不安視する向きもある。
耐えるしかない欧州
こういう状況を見て、プーチン大統領はガス供給を絞り、特に脆弱なドイツとイタリアを標的に、市民生活を直撃し、インフレを煽り、欧州経済に圧力をかけ、厭戦気分を醸成することを思いついたに違いない。小麦もそうである。ロシアがオデーサの食料倉庫を攻撃・爆破したとの報道があるが、世界的な食糧危機を更に進行させ、その責任を西側になすりつけることを思いついたのであろう。
欧州は耐えるしかない。ロシアの逆制裁を逆手に取ってエネルギーのロシア依存の脱却を急ぐしかないであろう。他方で、欧州連合(EU)はロシア原油の禁輸の徹底を急ぐ必要がある。
ロシア原油は中国とインドが調達を拡大しており、米欧の禁輸の実効性が失われている印象である――このような事態を防ぐために、ロシア原油を輸送するタンカーに対する海上保険の付与の禁止でEUと英国が合意したはずであるが、その効果を検証する必要があろう。
ロシアからみれば欧州連合(EU)が米英と足並みを揃えたことは、おそらく予想外だったでしょう。EUの中核国である独仏は米英よりもロシアに宥和的な姿勢をとってきました。EUは化石燃料をロシアに依存するなど経済的な結び付きも緊密です。その分だけ、EUによるロシアへの経済制裁の効果は高いですが、EU側が受ける痛みも大きくなります。
ロシアは、EUの脱ロシアの動きを座視するつもりはないでしょう。ロシアにとってもパイプライン・ガスの代替先の早期確保は難しいですが、ロシアにはEUが脱ロシア・ガスを実現する前に供給停止のカードを切り、揺さぶりを掛けることでしょう。
すでにロシアが一方的に決めたガス代金のルーブル建てでの支払いに応じなかったなどの理由で、ポーランド、ブルガリアに始まり、ドイツ、イタリアなどへのガス供給を停止・削減しています。ガスを巡るEUとロシアの攻防は、需要期となる今年秋口以降に向けて、激しさを増すことになるでしょう。
米国と欧州が国際社会を動員してロシアを政治的、経済的に孤立させようとする中で、あまり注目されなかった事象として、中国、インド、そして発展途上国の多くが乗り気でなかったことがあります。これは実利的な面もあります。
ロシアは世界の多くの地域にとって食糧、燃料、肥料、軍需品、その他の重要な商品の主要な供給国です。しかし、ロシア型の社会の腐敗、非自由主義、民族主義が、世界の多くの地域で、ルールではないにせよ、一般的であることも理由の1つです。世界の多くの国の指導者は、冷戦後の時代を形成してきた西側の制度や規範に対するプーチンの広範な拒否に共感しているようです。
ただ、このブログでもたびたび主張しているように、民主化は経済発展のためには欠かせません。民主化と経済は密接に関係しているのです。しばしば腐敗が取りざたされる、韓国は民主国家なのかというのは疑問があるところですが、それでも中露からみれば、はるかに民主化が進んでいます。
その韓国は現在ロシアのGDPを若干上回っています。しかも韓国の人口は約5000万人ですが、ロシアの人口は1億4000万人であるにもかかわらずです。これは韓国の一人あたりのGDPがロシアのそれを大幅に上回っているからです。
中露の一人あたりのGDPは10000ドル強にすぎません。これは、韓国はもとより、台湾や、バルト三国よりもかなり低いです。
なぜ、このようなことになってしまうかといえば、先進国においては民主化を進めた結果、多く中間層を輩出し、これらが自由に社会経済活動を行い社会のありとあらゆるところでイノベーションを起こし、富を生み出すことになるのですが、民主化が進んでいない中露などでは、政府などか大規模な投資をしてイノベーションを行ったにしても、西欧諸国のような大規模で、星の数ほどのイノベーションにはなりえず、結果として経済が発展しないのです。
このグラフ、相関係数が0.7 となっていますが、これは社会現象の相関係数としてはかなり高い数値です。
欧米の指導者たちは、世界を気候変動から救うという名目で、発展途上国に対して自国の石油やガス資源の開発、および化石燃料へのアクセスによって可能になる経済成長をあきらめるよう促してきました。
先進国経済が今でも化石燃料に大きく依存していることから、アフリカをはじめとする途上国政府は、これを当然ながら偽善と判断することになります。一方で貧しい国々では石炭火力発電を段階的に廃止するよう提唱しているのです。富裕国政府は、自国の資源を利用し続けながらも、貧しい国々の化石燃料インフラ整備に対する開発資金をほとんど断ち切っているのです。
恨みは深いです。何十年もの間、欧米の環境NGOやその他のNGOは、政府や国際開発機関の間接的なあるいは直接的な支援を受けて、ダムから鉱山、石油・ガス採掘に至るまで、大規模なエネルギー・資源開発に幅広く反対してきたのです。
NGOの環境問題や人権問題に対する懸念は、たいてい本物です。しかし、これらの問題に対する欧米の取り組みが十字軍的で、しばしば恩着せがましいのは、NGOの地元キャンペーンが主に欧米によって資金が出され、人員が動員され、組織化されているという事実と結び付き、植民地時代から続く反欧米の深い溝を生み出してしまっているのです。
日本人はこれを理解するのは難しいかもしれませんが、未だにくじらの町太地町に居座る、環境保護団体を思い浮かべると理解しやすいと思います。特にオーストラリアの保護団体の活動は執拗なものでした。オーストラリア人活動家の押し付けがましい発言や、自分たちが絶対に正しいという信念からの無謀な行動をみて反発しなかった日本人はいなかったでしょう。
途上国に対する NGO の働きかけは、日本に対する鯨問題へのいやがせのスケールをはるかに上回るものであり、途上国の大きな怒りを買うことになったのです。
一方中露は環境問題などに躊躇せず、エネルギー、資源採掘、インフラへの投資をテコに途上国における地政学的利益を拡大してきました。その意図は、モスクワと北京の経済的優先順位を高める形で開発途上国の依存関係を構築し、かつ国際的な影響力を生み出すことです。ウクライナ侵攻以来、この戦略の有効性は誰の目にも明らかになりました。
ロシアのウクライナ侵攻、先進国による対ロ制裁を契機に、先進国と新興国との間には一気に軋轢が強まっています。そのため、G7は有効な対策を打ち出すことが難しくなっており、この点は今回のG7サミットでも改めて浮き彫りとなっています。
先進国としては環境問題では、発展途上国が化石燃料を用いて産業を起こしても、当初はそれはわずかなものであり、さほど問題にはならないはずですから、発展の段階に応じて、それを要求するようにすべきです。人権問題に関しては、人権問題自体だけを問題にするだけではなく、人権を重視しないような非民主的国家では経済発展しようがないことを中露などを例にとってわかりやすく啓蒙していくべきです。
そのプロセスを欠いて、いきなり環境問題や、人権問題に走るから反発されるのです。
ウクライナ産の小麦に依存するアフリカ・中東諸国の国々は、価格高騰のみならず、戦争の影響でウクライナ産の小麦の入手が難しくなっています。そうしたもとで、多くの国が輸出制限を実施していることが、食料危機をより深刻化させています。
G7サミットではバイデン米大統領が途上国へのインフラ整備支援を打ち出したのですが、これは、中国の「一帯一路戦略」に対抗するものです。世界経済が抱える課題に対応するというよりも、先進国の利害に強く関わる政策です。世界のリーダーたちが、国を超えて世界全体が抱える諸問題への対応を推進する、という本来のG7の意義は後退してしまっているのではないでしょうか。
フィンランドに拠点を置く独立系の「エネルギー・クリーンエアー研究センター(CREA)」がまとめた報告書では、ロシアの戦費は1日あたり約8億7600万ドルと見積もられています。
一方、CREAは、ロシアはウクライナにおける紛争が始まった2月24日から6月3日までの100日間に、化石燃料の輸出で970億ドルの収入があったとしています。1日に換算すれば9億7000万ドル程度です。ロシアの戦費は化石燃料の輸出による収入で賄われたことになります。
取引価格を一定水準以下に抑えることを、石油タンカーでの船舶保険の利用条件とする案が浮上しているといいます。しかし、そうした枠組みが本当に有効に働くかどうかは疑問です。実際には、ロシア産原油の輸出を抑制することに一定程度働く一方、一段の価格高騰を招くことにはならないでしょうか。
考えれば考えるほどロシアの先行きは暗いですが、「何があっても確実にロシアに残るもの」も少なからず存在する。例えば以下のような要素です。
(1)地球上の陸地面積の6分の1を占める広大な国土
(2)潤沢な地下資源(ただし効果的に使えるかどうかは不明)
(3)安保理常任理事国の地位(拒否権は永遠)
(4)膨大な量の核兵器
ロシアは、世界最大の国土面積を有する巨大国家です。万一誰かに攻め込まれた場合には、戦略縦深の後退によっていくらでも時間を稼ぐことができます。その上で正規軍とパルチザンによる反撃が可能です。つまり守りに対しては絶対的に強いのです。ロシアは過去においては海外から攻め込まれたときの勝率は100%です。
ただし自分たちが他国に攻め込んだときはその限りではありません。露土戦争(1877年~1878年)は負けているし、日露戦争(1904年~1905年)もそうです。今回の対ウクライナ戦争も、多分にその公算が大です。守りの絶対王者は、攻めに回ると意外と心許ないのです。それでも、他国に攻め込まれて白旗を掲げる、ということだけは考えにくいです。最後は必ず、プーチンを相手に「交渉」という形で終わらせることになるのでしょう。
「この戦争によってロシアが新たに得るもの」も検討しなければならないです。それはおそらく「中国との腐れ縁」ということになるのではないでしょうか。
すでにロシアからは、欧米を中心に1000社近くが撤退しているなか、中国企業の「残留」が目立ちます。
西側のグローバル企業がどんどん撤退する中で、ロシア・ビジネスは彼らには「おいし過ぎて止められない」のではないでしょうか。対ロシア経済制裁が長期化し、西側企業の撤退が続くにつれて、その穴を埋めるのは中国企業ということになるのでしょう。
ロシア産の資源をアジア勢がディスカウント価格で買っているお陰で、国際商品価格の上昇に歯止めがかかっているという現実もあります。いずれにせよ、こういう状況が続くにつれて、ロシアは中国のジュニア(立場の低い)・パートナーとなることが避けられないのではないてしょうか。
サンクトペテルブルクで開かれた17日の国際経済フォーラムでプーチン大統領は、軍事同盟ではない欧州連合(EU)へのウクライナ加盟を容認する姿勢を見せる一方で、それはウクライナの「半植民地化」を意味するとしました。プーチン大統領は強気姿勢を維持するのですが、海外からの資金調達、支援が得られない中で戦争を続ければ、ロシア経済は一段と悪化していくことになります。
海外企業のロシア国内での事業停止・撤退の痛手も今後本格的に出てきます。そうしたなか、ロシアは中国に一段と接近し、経済面では中国の「半植民地化」することを受け入れないと、この先、経済の発展は望めなくなるのではないでしょうか。
 |
| プーチンと習近平 |
ただ、先程述べたように、中露の一人あたりのGDPは両国とも10000ドルに過ぎません。中国はロシアの10倍の人口を擁しているから、経済も10倍なのであって、経済発展のノウハウなどありません。
実際このブログでも以前述べたように、バルト三国等の東欧諸国が、当初中国の「一帯一路」の投資を受け入れたのは、国民一人ひとりを豊かにしたいと考えたからでしょう。しかし、バルト三国より一人あたりのGDPが低い中国にはもともとそのようなノウハウも知識もありません。
東欧諸国が失望するのも、最初から時間の問題だったといえます。
ロシアは中国のジュニア(立場の低い)・パートナーとなって、中国の投資を受け入れたとしても、経済発展は望めません。せいぜい、ウクライナ戦争開始前の水準に戻すことは、ひょっとするとできるかもしれませんが、それ以上は望めません。
中国は過去には、国内で大規模なインフラ投資をしてきたので、経済発展してきたのですが、いまや投資が一巡して、国内では目ぼしい投資案件がなくなったため、「一帯一路」に望みをかけたのでしょうが、そもそも経済発展のノウハウがない中国が海外投資で、地元国を潤わせさらに、自らも潤うなどという芸当はできません。
ロシアも復興のためには、中国の支援を受け入れるかもしれませんが、その後も中国に頼り、中国のジュニア・パートナーであり続けることはないでしょう。

.jpg)
.jpg)