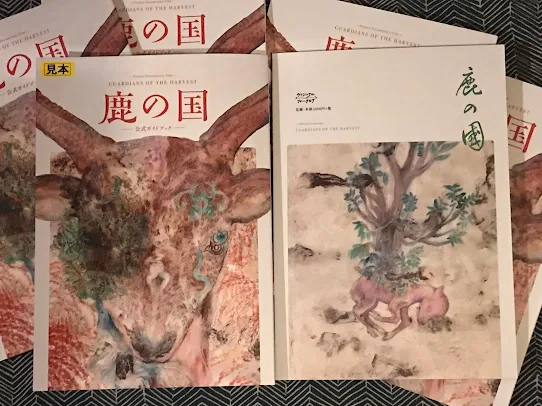まとめ
- 日本外務省の中国修学旅行安全注意喚起に対し、中国外務省が「リスク誇張」と批判、不満表明。
- 中国は「安全な国」と主張、日本に注意喚起の是正と交流雰囲気改善を要求。
- 在日中国大使館が日本での事件を理由に安全対策呼びかけ、中国政府の責任と主張。
これに対し、中国外務省の郭嘉昆報道官は22日の記者会見で、「中国は開放的で安全な国」と強調し、日本側の注意喚起は安全リスクを悪意で誇張し政治的意図があると批判。「強烈な不満」と「断固たる反対」を表明し、厳正な申し入れを行ったと明らかにした。
また、日本に誤った措置の即時是正と中日間の人的交流の良好な雰囲気作りを求めた。一方、在日中国大使館は17日、日本での無差別殺人や食中毒事件を挙げ、中国人旅行者に安全対策強化を呼びかけ。郭報道官は日本に安全リスク報道が多いとし、中国政府の注意喚起は責任と義務だと主張した。
【私の論評】中国危険レベル0に批判殺到!外務省の邦人保護放棄を糾弾
まとめ
- 外務省危険レベルの誤判断:事件多発でも中国を「レベル0」にし、危険軽視が批判される。
- 邦人保護の放棄:安全策ゼロで責任丸投げ、無責任と非難される。
- 対中忖度:他国が危険度を上げてもレベル0維持、外交優先と糾弾される。
- 危機管理の欠如:対応遅れと基準不明で「危機管理ゼロ」と酷評される。
- 信頼喪失:抗議続出で「子どもの命を危険に」と信頼を失う。
中国の傍若無人ぶりは今更批判する必要がないくらいに、多くの国民に知れ渡った事実である。しかし、日本の外務省はどうなのか。外務省のサイトを閲覧すると、確かに以下のURLで、修学旅行に対する注意喚起されていることが話わかる。
ただ、危険情報の地図では、中国西部は危険レベル1 になっているが、それ以外は何の指定もされていない。
中国本土の危険レベル0維持は、外務省の甘い治安評価と日中関係への過剰な忖度が生んだ愚策だ。2024年6月の蘇州での日本人母子襲撃事件、9月の深圳での日本人児童刺殺事件は、反日感情が絡んだ凶悪事件だったが、外務省は「局所的」と切り捨て、危険レベルの引き上げを拒否した(毎日新聞、2024年9月)。
新疆ウイグル自治区の2009年ウルムチ暴動やテロリスク、チベット自治区の2010年代デモ暴徒化と当局の監視がレベル1の理由だが、中国本土の他の地域はまるで安全地帯のように扱われている(外務省海外安全ホームページ、2025年2月25日更新)。
外務省が「中国を渡航先とする修学旅行等を検討される学校関係者の皆様へ」(www.anzen.mofa.go.jp)で修学旅行の注意喚起を出したのは、一部の高校が中国への修学旅行を計画し、国内で安全懸念が爆発したからだ。だが、この対応はXで「無責任」「学校に丸投げ」と叩かれ、保護者や議員から「子どもの命を軽視する」と非難の嵐が吹き荒れた(X投稿、2024年9月~10月)。
注意喚起は専用ページやスポット情報に留まり、危険レベルは動かず、「中途半端」の烙印を押された。米国は不当拘束や出国禁止リスクでレベル3を設定(2024年10月更新)、オーストラリアや韓国も高い危険度を維持するが、日本はレベル0に固執。他国との落差は滑稽を通り越し、怒りを呼ぶ(産経ニュース、2024年10月)。2023年8月のALPS処理水放出後の中国での抗議行動や邦人監視強化も、共同通信が報じた国家安全部門の動向とともに危険レベルに反映されず、対応の遅さが白日の下に晒された(共同通信、2023年9月)。
外務省の煮え切らない態度は、邦人保護を投げ出した無責任の極みだ。蘇州・深圳の事件で邦人の命が脅かされたのに、危険レベル0を維持し、曖昧な注意喚起でごまかすのは危機管理の放棄である。Xでは「外務省は無能」「子どもの命を危険に晒すな」と怒りが爆発した(X投稿、2024年9月~2025年1月)。2023年5月と2024年5月の外務委員会で、自民党の西田昌司参議院議員が中国全域のレベル1指定を求めたが、林芳正外務大臣は「適時見直し」と繰り返し、進展はゼロだ(衆議院会議録、2023年5月、2024年5月)。
2024年12月、外務省高官が日中対話で修学旅行受け入れ促進を約束すると、立憲民主党の岡田克也議員が「安全を誰が担保するのか」と追及したが、外務省は「中国側と協議」と逃げた(朝日新聞、2024年12月)。2024年10月、東京都内の高校が中国修学旅行を計画した際、保護者の「外務省の注意喚起は役に立たない」との抗議が殺到し、計画は白紙に戻された(東京新聞、2024年10月)。
外務省は学校に旅行届を求めるだけで、警備は中国側に丸投げし、具体的な安全策は皆無だ。産経ニュースは、日本が環太平洋先進国で唯一中国をレベル0とする点を批判し、米国のレベル3との落差を問題視した(産経ニュース、2024年9月24日)。共同通信は、中国の国家安全部門が処理水問題で邦人監視を強め、拘束も検討と報じ、危険性の高まりを浮き彫りにした(共同通信、2023年9月)。
外務省の弱腰は過去にも繰り返された。2019年、香港の反政府デモが激化した際、香港をレベル1に設定したが、中国本土への波及リスクは無視し、批判を浴びた(読売新聞、2019年8月)。2022年、中国で日本人ビジネスマンが拘束された事件でも、危険レベル見直しはなく、企業から「邦人保護が不十分」との声が上がった(日経新聞、2022年6月)。
2023年9月、ALPS処理水放出後、中国で日本人学校への嫌がらせが増え、山東省の日本人学校が一時閉鎖されたが、外務省は「過剰反応を避けろ」と呼びかけただけで危険レベルは動かなかった(NHK、2023年9月)。
2024年11月、関西の私立高校の中国修学旅行計画に対し、保護者の反対署名が数百人分集まり、計画は中止に追い込まれた(読売新聞、2024年11月)。2024年8月、福岡の教育委員会が外務省に安全性を問い合わせたが、「学校の判断」と突き放され、委員会内で怒りが爆発した(西日本新聞、2024年8月)。2025年4月、西田昌司議員が「南京大虐殺記念館などを理由に修学旅行生は行かせられない」と発言し、外務省の修学旅行促進策に異議を唱えたが、外務省は明確な反論を示さなかった(政治知新、2025年4月20日)。
この外務省の怠慢は、対中関係を優先し、国民の命を軽視する裏切りだ。危険情報基準は非公開で、事件の評価は曖昧。国民の安全が脅かされているのに、明確な渡航制限や学校向けガイドラインは作らない。Xでは「腰抜け外交」「外務省は現実を見ろ」との声が響き、信頼は地に落ちた(X投稿、2024年9月~2025年1月)。この無責任な姿勢は許されない。危険情報基準の透明化、具体的な安全策の提示、邦人保護の覚悟を今すぐ示せ。外務省の怠慢は、国民の命を危険に晒す罪だ。
【関連記事】
二大経済大国、貿易戦争激化へ 中国報復、米農産物に打撃 トランプ関税―【私の論評】米中貿易戦争の裏側:米国圧勝の理由と中国の崩壊リスクを徹底解剖 2025年4月6日
<主張>日比2プラス2 新協定で対中抑止強化を―【私の論評】日比円滑化協定(RAA)の画期的意義:安倍外交の遺産と日本の新たな安全保障戦略 2024年7月9日
政府、中国大使発言に抗議 台湾巡り「日本民衆火に」―【私の論評】中国外交は習近平の胸先三寸で決まる、外交部長や大使等は他国に比較して地位も低く権限もない 2023年5月10日
中国が「対外関係法」を施行 米にらみ対抗姿勢を明記―【私の論評】中共が、何の制約も制限もなく、自由に外交問題に関与し、外国人を取り締まる体制を確立するその第一歩か 2023年7月1日