「中国経済は崩壊するのか」。
この問いは、極端な悲観論と根拠の乏しい楽観論のあいだを振り子のように揺れてきた。しかし現実は、そのどちらでもない。中国経済は今も動いている。工場は稼働し、街に人はいる。統計上のGDPも存在する。体制が崩壊しようが、何が起ころうが、そこには大勢の人々が存在しており、それらの人々が経済活動をする以上、経済が完全に崩壊することはない。
だが、問題はそこではない。
中国はすでに「回復不能点(ポイント・オブ・ノーリターン)」を静かに通過した。しかもそれは、単なる景気循環の話ではない。中国共産党がこれまで拠って立ってきた統治の正当性そのものが、成立しなくなったという意味である。
1️⃣経済成長と引き換えに成立してきた統治──「保八」が示していた正当性の最低条件
中国共産党は、選挙によって選ばれた政権ではない。王朝の血統を引き継いだわけでもなく、宗教的権威を持つわけでもない。建国以来、この体制が一貫して抱えてきた根本問題は、「なぜこの党が統治する資格を持つのか」という問いに、制度として答えを持たない点にあった。
毛沢東時代、この問いへの答えは革命の正当性だった。しかし革命の記憶は時間とともに薄れ、文化大革命という破局を経て、共産党はイデオロギーによる正当化を事実上放棄した。その代わりに選ばれたのが、改革開放以降の成果による正当化である。
政治的自由は制限する。言論も統制する。
だがその代わりに、国民の生活水準を引き上げる。昨日より今日が良くなり、今日より明日が良くなる。親より子が豊かになる。この「上昇の実感」こそが、中国共産党と国民のあいだに成立した暗黙の統治契約だった。
重要なのは、「8%」が経済的な理想値ではなく、政治的な最低条件だったという点だ。
急速な都市化、地方から都市へ流入する膨大な労働者、毎年吐き出される大学卒業生を吸収するには、それだけの成長が必要だった。だから地方政府は採算を度外視して投資を重ね、中央政府も成長率の維持を最優先してきた。
この時代、中国共産党の統治正当性は、かろうじて機能していた。自由の制約に不満を抱えながらも、人々は「まだ我慢する価値がある」と思えたからだ。
しかし今、中国経済は構造的にこの水準へ戻れない。人口動態は変わり、不動産依存は限界に達し、債務は積み上がり、生産性は伸びない。保八が常態だった時代の前提条件は、すでに失われた。
決定的なのは、「保八」が単なる数字ではなく、統治正当性の安全弁そのものだったという事実である。この安全弁が壊れた瞬間、成果による正当化は再生産できなくなった。いま起きているのは景気の上下ではない。統治の根拠そのものが枯渇し始めた局面である。
この結果、その歪みは統計や公式発表の中にとどまらず、都市の日常や人々の行動といった「数字に現れない領域」に、はっきりと姿を現し始めている。
2️⃣排水口のない成長モデルが招いた必然──国際金融のトリレンマと回復不能点
中国経済の行き詰まりは偶然ではない。国際金融のトリレンマ──資本移動の自由、為替の安定、独立した金融政策は同時に成立しない──という原理から見れば、中国がいずれ限界に達することは、かなり前から予見可能だった。
中国は、為替の安定と独立した金融政策を優先し、その代償として資本移動を厳しく制限する道を選んだ。この選択は体制維持としては合理的だったが、致命的な副作用を伴った。危機や過剰資本を国外に逃がせない構造を、自ら固定してしまったのである。
この構造は、排水口のない水槽に水を注ぎ続ける姿に似ている。水位は上がるが、余分な水を外へ流す仕組みがない。通常の市場経済では、余剰資金は海外投資として分散される。しかし中国では資本規制によってそれができず、資金は国内を循環するしかなかった。
その行き先が、不動産と地方政府融資平台である。採算が崩れても投資が止まらない異常な状態が長年続いたのは、この制度構造の必然だ。歪みは分散されず、時間をかけて国内に蓄積され、ついに表面化した。これが回復不能点の正体である。
米国の経済制裁や技術規制は、この到達を早めたにすぎない。原因ではない。中国経済は制裁で壊されたのではなく、排水口を塞いだまま成長を続けた結果、自壊したのである。
3️⃣数字に現れない経済停止と、長い内破の始まり
 |
| 廃墟と化した中国のショッピングモール |
この構造的限界は、すでに都市の風景に現れている。一線都市であっても、かつて行列が当たり前だったレストランは空席を抱え、週末の大型商業施設にも人影がまばらだ。地下鉄の混雑緩和も、効率化の成果ではない。通勤そのものが減っている結果である。
地方ではさらに深刻だ。工場は止まり、賃金の遅配や未払いが長期化している。重要なのは、これが一時的な不況ではなく、再起動の見通しが立たないまま時間が過ぎている点である。経済は「止まる」のではなく、「戻らない」状態に入りつつある。
若者も同様だ。問題は失業率の数字ではない。努力しても報われないという確信が広がり、抵抗でも革命でもなく、社会参加そのものから静かに離脱する態度が蔓延している点である。これは体制にとって、暴動よりも危険な兆候だ。
不動産問題は中間層との社会契約を直撃した。引き渡されない住宅、価値が半減した資産、返済だけが残るローン。市場調整は行われず、国有色の強い企業は延命され、損失は個人に押し付けられる。この構造は、体制の支持基盤を内側から侵食している。
ここで起きているのは急激な崩壊ではない。監視と統制が機能している以上、体制はすぐには倒れない。だがその代わりに進行しているのが、経済モデルと統治モデルが同時に寿命を迎える、長い内破である。
結論
中国経済は崩壊していない。しかし、回復できない地点をすでに通過した。それは同時に、「保八」に象徴される経済成長によって支えられてきた中国共産党の統治正当性が、もはや成立しない地点でもある。
この帰結は、外圧によって生まれたものではない。国際金融のトリレンマの下で排水口を塞ぎ、歪みを国内に蓄積し続けた国家モデルの必然的な帰結である。
中国で起きているのは景気循環の失速ではない。
統治の前提そのものが、静かに、しかし確実に崩れ始めているという現実である。
中国の縮小は止まらない── アジアの主役が静かに入れ替わる「歴史の瞬間」が目前に迫る 2025年12月13日
人口、不動産、地方財政、若者雇用──個別なら耐えられた問題が同時に噴き出す中国の現状を、構造から整理した記事だ。中国の「縮小」が、単なる不況ではなく、地域秩序を揺るがす不安定化につながることが分かる。
中国は戦略国家ではない──衰退の必然と、対照的な成熟した戦略国家・日本が切り拓く次の10年 2025年12月11日
「中国は長期戦略国家だ」という通俗的イメージを覆し、体制維持が政策を歪めてきた現実を描く。経済の回復不能点が、統治の限界と直結していることを理解するための補助線となる。
中国で「ネズミ人間」が増殖中…その驚きの正体とは? 2025年4月27日
若者の大量失業と無気力化が、中国社会を内側から蝕んでいる実態を描く。数字では見えない「希望の消失」が、成長モデルと統治モデルの同時崩れを加速させていることが実感できる。
〈ソ連崩壊に学んだ中国共産党〉守り続ける3つの教訓と、習近平が恐れていること 2024年10月23日
中国共産党が最も恐れているのは外圧ではなく内部崩壊であることを、ソ連の教訓から読み解く。経済失速と統制強化が、かえって体制を脆くしていく構図が浮かび上がる。
習近平の中国で「消費崩壊」の驚くべき実態…! 2024年9月3日
上海や北京ですら外食・消費が急減している現実を具体的に示す。消費の冷え込みが雇用、税収、地方財政へ連鎖し、最終的に統治の基盤を削っていく流れが理解できる。











.jpg)
.jpg)
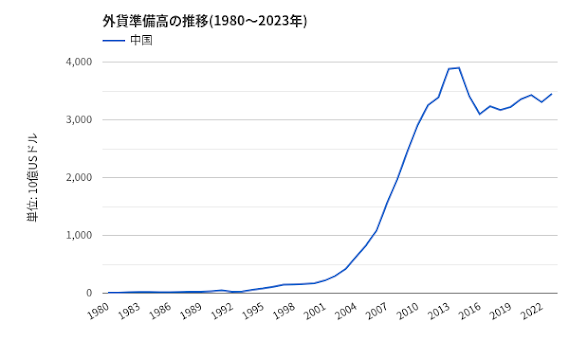
.jpg)


.jpg)



.jpg)
.jpg)












