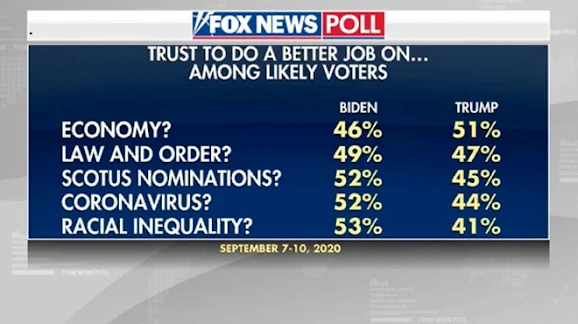■
岡崎研究所
元来会談は3月10日に始まる予定であったが、ガニ大統領がタリバンの捕虜の釈放を渋り、反発したタリバンが政府軍への攻勢を強めたため、交渉開始が遅れていたものである。
タリバンとアフガン政府代表の会談に先立ち、米国とタリバンが2月にドーハで会談し和平合意を達成している。そこでアフガン政府がタリバンの捕虜5,000人を、タリバンがアフガン政府軍の捕虜1,000人を釈放することが合意された。
アフガン政府抜きで交渉が行われたことはアフガン政府にとっては屈辱的なことであったろうが、アフガンでの現状を反映したものであった。ガニ大統領はタリバンの5,000人の捕虜、特にそのうちの400人の重罪捕虜の釈放を渋った。おそらく米国のハリルザド特使の説得があったのであろうが、ガニ大統領は400人の重罪捕虜の釈放については、国民大会議(ロヤ・ジルガ)の判断を仰ぐとの決定をし、国民大会議が9月10日にようやく釈放の決定をしたものである。
今回のアフガン和平交渉を推進したのはトランプ大統領であった。トランプは2016年の大統領選挙でシリア、イラクに加えてアフガニスタンからの米軍撤兵を公約に掲げ、そのためアフガンでの和平交渉を推進しようとした。
トランプはまず駐アフガン米兵を12,000人から8,600人に削減し、ついで11月までに4,500人まで削減することを決定した。2月のタリバンとの和平会談で、タリバンがアフガン国土をテロ攻撃に使わないという約束をすれば、米軍とNATO加盟国の軍を14か月以内に(来年4月ごろ)完全撤収することに合意した。
これは二つのことを意味する。一つはトランプの当初の希望にもかかわらず、大統領選挙までの完全撤退はないということである。トランプも現実を認めたことになる。
第二は、タリバンが約束を守れば米軍が完全撤退することである。米国政府の中には、アフガンの治安部隊の訓練のため4,000人前後の米兵は残すべきであるという見解があったが、その見解は採用されなかったことになる。米国はもしタリバンが約束を破ったら完全撤退はすべきでない、という意見もあるが、タリバンから見れば、約束を守れば14か月以内に米軍とNATO軍が完全撤退することが合意されているので、来年4月ごろまで約束を守るようにするのではないだろうか。
もしバイデン大統領が実現したらどうなるか。バイデンは以前からアルカイダの復活を阻止するために小規模なテロ対策部隊は残すべきであるとの見解を持っていたことで知られている。バイデンは以前から米国のアフガンに対するコミットメントには懐疑的であったので、仮に完全撤退となっても反対はしないのではないかと思われる。その背景は米国世論のアフガン疲れである。9.11直後は、アルカイダ撲滅のためアフガンへの軍事攻撃を全面支持したが、その後アフガンの米国にとっての重要性が急速に薄れたこともあり、米国世論は米軍の全面撤退を支持するだろう。
タリバンとアフガン政府の交渉は当然のことながら難航することが予想される。アフガン政府は統治の形態をめぐって、たとえば民主的選挙と女性の権利を定めた憲法を受け入れなければならないと主張し、タリバンは難色を示すだろう。合意の成立が容易でないことは周知の事実である。しかし、交渉が始まったこと自体画期的で、軍事的解決の選択肢がない以上、何とか妥協点を見出すための努力が行われ、米国や関係国も支援の手を指し伸ばすこととなるだろう。
以下に現在のアフガニスタン戦争がどのように始まり、どのような経過をたどり現在に至っているのか簡単に整理しておきます。
 |
| 9.11同時多発テロ |
米国は、ターリバーン政権の拒否を見越して武力行使を準備、周辺国への根回しを開始しました。また国連安全保障理事会、NATO、EUなども次々とテロへの非難決議を採択し、ロシア・中国を含む60ヵ国以上がアメリカ合衆国を支持する声明を発しました。
一方でブッシュ大統領は、この戦いはイスラーム教徒を相手にする十字軍の戦い「クルセード」と表明し、世界各地のイスラーム教徒の反発が起きたため発言を取り消したが、イスラーム圏では反米暴動が各地で起きました。
10月7日、米・英軍(有志連合)はインド洋の艦船から戦闘爆撃機による攻撃を開始、また潜水艦から巡航ミサイルを発射して、カーブルのターリバーン政権中枢やアルカーイダの訓練所などの空爆を開始しました。
この空爆でアフガンに投下された爆弾は、第二次世界大戦中、1941年から42年のロンドン大空襲でドイツ軍が投下した爆弾の半分に相当する1万トンに達しました。空爆に加えて、武器や砲弾の援助を受けた反ターリバーンの「北部同盟」が攻勢に出て、マザリシャリフ、ヘラート、首都カーブルを制圧しました。アメリカ・イギリス地上部隊は最後のターリバーンの本拠カンダハール攻略に参加しました。こうして戦闘2ヶ月でターリバーン政権は崩壊しました。
米軍の支援のもとで戦った「北部同盟」は、もともとはターリバーンの主体であるパシュトゥーン人以外のアフガン人であるタジク人やウズベキ人の部族長が寄り集まった軍閥集団で、かつてのソ連軍の侵攻の際には、パシュトゥーン人もその他の部族もゲリラ兵として協力して戦った仲間でした。
米軍に支援された北部同盟は、2001年末までにターリバーン政権を首都カーブルから追い出し、権力を奪回しました。これによってアフガニスタン人同士だけで戦う「アフガニスタン内戦」から、米軍・政府軍対ターリバーンという構図の「アフガニスタン戦争」に転化したと言えます。
また、米兵に助けられている政府軍よりもターリバーン兵(最も彼らもパキスタンやサウジアラビアの支援を受けていたと言われているが)を味方と感じる者が多く、ターリバーンの勢力はじりじりと回復していきました。
2003年のイラク戦争勃発によって世界の関心はアフガニスタンから離れていったこともあり、日本もふくめた世界の多くが知らないまま、アフガニスタンではターリバーンが国土の約半分を支配するほどになっていました。
2009年に登場したオバマ政権も米軍の撤退には踏み切れず、状況の悪化から帰って増派すると声明しました。しかし、再選時にはアフガニスタンからの段階的撤退を公約、2014年12月にはNATOが主導する国連治安支援部隊(ISAF)が公式に任務を終了しました。
そのかわりに米軍が「確固たる支援任務」と証する部隊を駐留させ、政府軍の支援と指導に当たることになりました。この部隊はNATO主導とは言え、実態はアメリカ軍で、なおも1万3000人の米兵が駐留しました。
 |
| 「国際治安支援部隊」から「確固たる支援任務」への移行式典(2014年12月8日カブール) |
このように米軍はアフガニスタンからの撤退を先延ばしにするうちに、2001年から2020年まで20年経過し、今までのアメリカの関わった戦争で最も長かったベトナム戦争(一般的に1955年~1975年とされる)とほぼ同じ最長の戦争となってしまったのです。
米国はタリバンが国際テロ組織に協力しないなら米軍は、撤退するという立場です。アフガニスタンからの米軍撤退は既定路線ですが、イスラム国は同国で勢力を拡大中です。タリバンがアルカイダを受け入れなくても、イスラム国は既に勝手に侵入して地盤を固めつつあります。アフガニスタンは、イスラム過激派にとっては外人に邪魔されず存分に戦える安全地帯となりそうです。
トランプ大統領は「和平」協定合意に向けタリバンともアフガニスタン政府とも話し合いがうまく進んでいると発言していました。「和平」協定と言っていますが、彼の目的は20年近く続いた米軍の駐留を終わりにすることであって、アフガニスタンに「和平」をもたらすことではありません。
しかし、だからといつて米国を責めるべきでもありません。米国の判断は正しいともいえるでしょう。確かに米軍の撤退は、アフガニスタンに和平をもたらすわけではありませんが、アフガニスタンで紛争が続き、米国からの支援もないということになれば、いずれ決着がつき、新たな秩序が形成されるからです。
そのほうが、米国が中途半端に関与し続け、紛争が更に長引くよりは良いと思います。これが2001年の時点では事情が違います。あの時はアルカイダがアメリカを攻撃したので多くの米国人も米国のアフガニスタン関与を支持したのです。
ところがその後は、違います。オバマ大統領がアフガニスタンで行ったのは、すべてのアフガニスタン人を救って民主制度を根付かせるというものです。
もちろんアフガニスタン側も米兵と一緒に喜んで写真に写ったりしたわけです。なぜなら米国から700億ドルもの資金が流れ込んでくるからであり、そのうちのいくつかはオーストラリア人が使い、カブール政府が受け取ったり、結局豪華な邸宅やイタリア製の配管などに化けたりしたわけです。
 |
| アフガニスタン国民軍の女子戦術隊による作戦訓練。この女性兵士の 特殊部隊は、女性と児童の捜査、訊問、医療支援などに従事(2018年) |
このようなアフガニスタンやイラクの民主化というのも、時間がたつとその熱が冷めてきます。それが、今回の米軍の撤退に結びつくわけです。
ところがもう一つ戦争が長引いた原因があります。こっちはかなり真剣に見ていかなければなりません。
その原因は長期的に、世界中で行われている紛争と同じものであり、そうしてこれは間抜けな外部からの介入が原因であり、その動機は人間の最高の「善意」にあるのです。
先日もこのブログで掲載したように、米国の戦略化ルトワックは『戦争にチャンスを与えよ』で、紛争等に関わるなら正規軍を50年くらいは派遣して、秩序をつくりかえるくらいの気構えが必要であって、中途半端に関わるのは混乱を増すだけだと言っています。
アフガニスタンも、この例に漏れません。米国はアフガニスタンに関与するなら、爆撃等だけで終了しすぐに撤退するか、本気で介入するなら中途半端をせずに、最初から50年くらいも正規軍を大量に派遣するつもりで、秩序をつくりかえるのか、はっきりさせるべきでした。
しかし、中途半端な介入をしてしまったため、結局ほとんど何も変えられなかったのです。米軍はアフガニスタンに行って、アフガニスタンの伝統的な生き方をやめさせようとしました。しかし、先日新聞の意見欄にも書かれてましたが、米軍が何年間も介入したにもかかわらず現地の女性は抑圧されたままです。