 |
| 中国経済が変調すれば、習近平主席の地位も危うくなるが、他国にとっては歓迎すべき事態か |
トランプ米政権に貿易戦争を仕掛けられた中国が大揺れだ。世界第2位の経済大国が「経済敗戦」となった場合、習近平政権に大打撃となるのは確実だが、世界経済も大混乱しないのか。中国経済や市場に詳しい国際投資アナリストの大原浩氏は、むしろ「世界経済は好転する」とみる。その理由について緊急寄稿した。
「米国との貿易戦争で中国の負けは確定している」というのが筆者の持論だが、中国が崩壊でもしたら世界経済はどうなるのか? と心配する読者も多いかもしれない。しかし、結論から言えばごく短期的な負の影響はあっても、長期的に考えて中国崩壊は世界経済にプラスに働く。
そもそも、現在の世界経済の最大の問題は「供給過剰」である。1979年からトウ小平氏によって始められた「改革・開放路線」は、89年のベルリンの壁崩壊、91年のソ連邦崩壊の後、92年ごろから加速した。80年代ぐらいまでは「鉄のカーテン」や「竹のカーテン」で西側先進諸国と隔絶されていた共産主義諸国が、大挙して世界の貿易市場に乗り出してきたという構図だ。
東南アジアや南米などの新興国も供給者として名乗りを上げた。それまで日本と欧米先進諸国以外にはシンガポール、香港、タイ、台湾、韓国程度しかプレーヤーがいなかった市場環境は大きく様変わりした。
日本のバブル崩壊は90年ごろだが、世界的な供給過剰が始まる時期と重なったのが不幸であった。今後、もし中国が崩壊し莫大(ばくだい)な供給がストップすれば、日銀が目標に掲げる物価上昇率2%もやすやすと達成でき、日本経済は短期的な波乱を乗り越えながら力強い発展を続けるだろう。
忘れてならないのは生産性の向上である。経営学者のピーター・ドラッカー氏によれば、「科学的分析」が生産に取り入れられて以降、工業製品の生産性は50倍以上になっている。つまり50分の1の人手で足りるというわけだ。
 |
| 経営学の大家ピーター・ドラッカー氏 写真はブログ管理人挿入 以下同じ |
20~30年前にはハードディスク50メガバイトのパソコンが30万円ほどしたが、今やそれは数千円のUSBレベルであるし、1本1万円ほどした映画のDVDは、月額1000円ほどで見放題である。
だから、中国1国が“消滅”したくらいでは世界、そして日本への商品供給は途絶しない。生産性の向上ですぐにカバーできる。
このような供給過剰の世界で、いくら資金を供給しても物価が上昇しないのはある意味当然かもしれない。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が金利引き上げを2019年で打ち止めにする意向を表明した後、トランプ大統領が「金利引き上げは望ましくない」と述べたが、供給過剰社会で金利の引き上げは困難だ。これは欧州においても同様だ。
歴史的には、世界大戦級の大規模な戦争が供給過剰を解消してきたが、今回は中国の崩壊によって世界経済が好転するかもしれない。その方が、はるかに世界にとってプラスだといえる。トランプ氏がそこまで考えて中国を経済的に「攻撃」しているのならあっぱれだといえる。
国防・セキュリティー問題での中国企業への厳しい制裁、中国製品への貿易関税、さらには「北朝鮮」問題も実は中国を押さえ込む導火線の役割を果たしていたのかもしれない。今回の一連の動きは「中国外し戦略」といっても良いだろう。
いずれにせよ、今のトランプ氏の言動を見ている限り「米国という偉大な国にたて突く中国など無くなってもかまわない」という気迫を感じる。
■大原浩(おおはら・ひろし) 人間経済科学研究所執行パートナーで国際投資アナリスト。仏クレディ・リヨネ銀行などで金融の現場に携わる。夕刊フジで「バフェットの次を行く投資術」(木曜掲載)を連載中。
 |
| 大原浩氏 |
【私の論評】中国崩壊の影響は軽微。それより日銀・財務官僚の誤謬のほうが脅威(゚д゚)!
ブログ冒頭の記事、結構納得できるところが多いです。まずはソ連が崩壊した時のことを考えると、確かソ連崩壊後のロシア国内は酷い有様となりましたが、ではそれによって日本をはじめとする他国がそれによって甚大な影響を被ったかどうかいといえば、まず日本についてはほとんど影響はなかったと思います。
これは、経済統計をみたとかそういうことではなく、その当時にリアルタイムで生きて経験したということからいうと、その影響についてはほとんど記憶にないです。さらに、「ソ連崩壊の世界への影響」「ソ連崩壊の日本への影響」などというキーワードでGoogleで検索してみましたが、これに該当する内容はありませんでした。試みに、この時代を生きていた私以外の他の複数の人々にも聞いてみましたが、誰も記憶している人はいませんでした。
これから類推するに、ソ連崩壊の影響は少なくとも、日本経済に及ぼす影響は軽微もしくは、ほとんどなかったのだと思います。もし、大きな影響があれば、誰かが記憶しているとか、少なくともGoogleで検索すれば何かの記録が出てくるはずです。どなたかこの方面に詳しいかたがいらっしゃいましたら是非教えていただきたいです。
直感的には、ソ連が崩壊しても、ほとんど影響がなかったというのであれば、たとえ中国が崩壊したとしても、世界経済に悪影響はほとんどないのではとの考えは間違いではないと思われます。
さらに、日本のことを考えると、そもそも、中国への輸出はGDP(国内総生産)比3%未満であり、投資は1%強でしかありません。この程度だと、無論中国に多大に投資をしていた企業は悪影響を受けるかもしれませんが、日本という国単位では、他国への輸出や投資で代替がきくので、日本経済にはほとんど影響がないといえそうです。
米国では、輸出そのものがGDPに占める割合は10%を切っています。さらにその中の中国といえば、数%にすぎません。これも、他国への輸出で十分に代替えがきくものと思われます。
さて、ブログ冒頭の記事では、生産性の向上による、供給過剰ということが掲載されてました。これは実際そうです。
それについては、以前のこのブログにも掲載したことがあります。その記事のリンクを以下に掲載します。
世界が反緊縮を必要とする理由―【私の論評】日本の左派・左翼は韓国で枝野経済理論が実行され大失敗した事実を真摯に受け止めよ(゚д゚)!
 |
| 野口旭氏 |
ところが、近年の世界経済においては、状況はまったく異なる。「景気過熱による高インフレ」なるものは、少なくとも先進諸国の間では、1990年代以降はほぼ存在していない。リマーン・ショック以降は逆に、日本のようなデフレにはならないにしても、多くの国が「低すぎるインフレ率」に悩まされるようになった。また、異例の金融緩和を実行しても景気が過熱する徴候はまったく現れず、逆に早まった財政緊縮は必ず深刻な経済低迷というしっぺ返しをもたらした。世界経済にはこの間、いったい何が起こったのであろうか。
一つの仮説は、筆者が秘かに「世界的貯蓄過剰2.0」と名付けているものである。世界的貯蓄過剰仮説とは、FRB理事時代のベン・バーナンキが、2005年の講演「世界的貯蓄過剰とアメリカの経常収支赤字」で提起したものである。バーナンキはそこで、1990年代末から顕在化し始めた中国に代表される新興諸国の貯蓄過剰が、世界全体のマクロ・バランスを大きく変えつつあることを指摘した。リマーン・ショック後に生じている世界経済のマクロ状況は、その世界的貯蓄過剰の新段階という意味で「2.0」なのである。
各国経済のマクロ・バランスにおける「貯蓄過剰」とは、国内需要に対する供給の過剰を意味する。実際、中国などにおいてはこれまで、生産や所得の高い伸びに国内需要の伸びが追いつかないために、結果としてより多くの貯蓄が経常収支黒字となって海外に流出してきたのである。
このように、供給側の制約が世界的にますます緩くなってくれば、世界需要がよほど急速に拡大しない限り、供給の天井には達しない。供給制約の現れとしての高インフレや高金利が近年の先進諸国ではほとんど生じなくなったのは、そのためである。
この「長期需要不足」の世界は、ローレンス・サマーズが「長期停滞論」で描き出した世界にきわめて近い。その世界では、財政拡張や金融緩和を相当に大胆に行っても、景気過熱やインフレは起きにくい。というよりもむしろ、財政や金融の支えがない限り、十分な経済成長を維持することができない。ひとたびその支えを外してしまえば、経済はたちまち需要不足による「停滞」に陥ってしまうからである。それが、供給の天井が低かった古い時代には必要とされていた緊縮が現在はむしろ災いとなり、逆に、その担い手が右派であれ左派であれ、世界各国で反緊縮が必要とされる理由なのである。相対的にモノが不足していた、旧来の世界とは異なり、現代の世界は貯蓄が過剰であり、その結果供給が過剰なのです。
このような世界ではよほど世界需要が急激に拡大しない限り、供給の天井には達しないのです。その結果として、高インフレや高金利が近年の先進国では生じなくなったのです。
このような世界においては、確かに中国が崩壊したとしても、日本や米国のようにGDPに占める内需の割合が多い国では、ほとんど影響を受けないでしょうし、輸出などの外需の多い国々では、たとえ中国向け輸出が減ったにしても、中国になりかわり、中国が輸出して国々に輸出できるチャンスが増えるということもあり、長期的にはあまり影響を受けないことが十分にあり得ます。
日本や米国が貿易戦争で甚大な悪影響を被ると考える人々は、両国のGDPに中国向け輸出が占める割合など全く考えていないか、あるいは過大に評価しているのではないかと思います。
今でも一部の人の中には、「日本は貿易立国」と単純に信じ込んでいる人もいます。こういう人たちは、過去の日本は、輸出がGDPに占める割合が、50%とかそれより多いくらいと思っているかもしれません。それは全くの間違いです。20年前は、8%に過ぎませんでした。これは、統計資料など閲覧すれば、すぐにわかります。
ただし、日本で一番心配なのは、過去に日銀官僚や大蔵・財務官僚らが、数字を読めずに、なにかといえば金融引締めと、緊縮財政を実施してきたという経緯があることから、彼らは世界が需要過多の時代から、供給過剰の時代に変わったといことを理解せずに、またまたやってはならないときに金融引締めと緊縮財政を実施してしまい、再度「失われた20年」を招いてしまうという危険です。
実際、2019年10月より、10%増税の実施が予定されていますが、自民党政権がこれに抗えず、これが実行されれば、日本経済は再び甚大な悪影響を受けるのは間違いないです。これに加えて、物価目標が達成されないうちに、日銀が金融引締めに転ずることになれば、今度は失われた20年どころか、「失われた40年」になりかねません。とんでもないことになります。
現実には、中国がどうのこうのなどという問題よりはこちらの問題ほうがはるかに大きいです。
【関連記事】
日銀、緩和策で国債大量購入 総資産、戦後初の「直近年度GDP超え」548兆円―【私の論評】何かにかこつけて、「緩和出口論」を語る連中には気をつけろ(゚д゚)!
世界が反緊縮を必要とする理由―【私の論評】日本の左派・左翼は韓国で枝野経済理論が実行され大失敗した事実を真摯に受け止めよ(゚д゚)!
日銀官僚の理不尽な行動原理 金融機関重視する裏に天下り…政策に悪影響なら本末転倒だ―【私の論評】日銀は銀行ではなく日本国民のために、金融政策に集中すべき(゚д゚)!
お先真っ暗…韓国「雇用政策」大失態、貿易戦争も直撃、対中輸出3兆円減の試算も―【私の論評】金融政策=雇用政策と考えられない政治は、韓国や日本はもとより世界中で敗退する(゚д゚)!
【日本の解き方】インフレ目標は断念すべきか 「2%」設定は雇用に劇的効果、財政問題解消のメリットあり―【私の論評】雇用が確保されつつインフレ率が上がらない状態は問題あり?なし?これで、インフレ目標の理解度がわかる(゚д゚)!











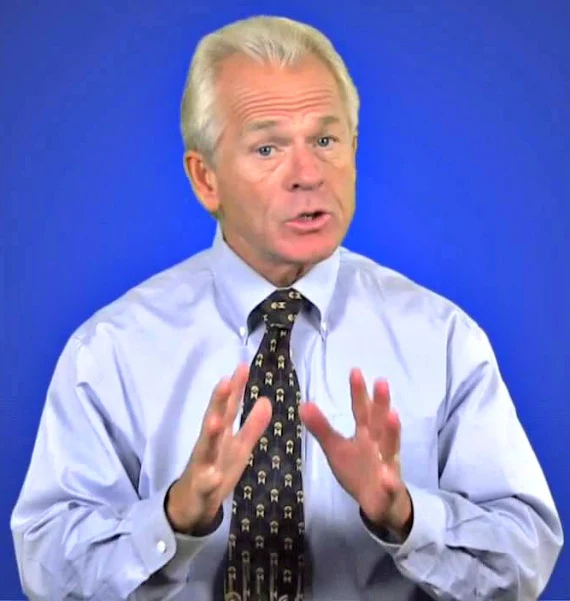



















.jpeg)

