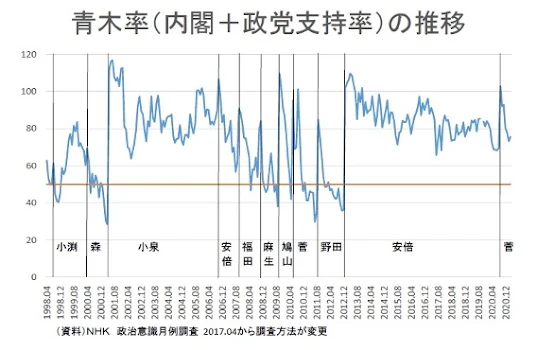|
中国はさきの全国人民代表大会(全人代=国会に相当)で、今年の経済成長率の目標を6%以上とする一方で、今年から始まる5カ年計画では成長目標を具体的な数字で示さなかった。これまでは必ず具体的な数値目標を明らかにしていただけに、極めて異例の対応だ。
中国政府は「成長率の高さではなく、経済の質と効率を重視しているため」と説明しているものの、先行きに不透明な要素を抱えているため数字を出したくても出せなかったとの見方が広がっている。
なぜなら、中国経済は深刻な構造問題を抱え、綱渡りの状況が続くことになりそうだからだ。最大の課題は失業問題だ。昨年来の新型コロナウイルスの感染拡大により、経営基盤の弱い中小企業が倒産し、個人事業主が職を失い、約2億人が失業状態にあるとの統計が発表されている。1年間に2億人は極めて深刻な数字だ。
際立つ中小企業の苦境ぶり
中国は米中貿易戦争で2019年に景気が大きく減速し、中小企業の苦境ぶりが際立っていたが、20年以降は新型コロナウイルスの感染拡大が追い打ちをかけた。米国ピーターソン国際経済研究所は、20年1~6月に中国全体の6%にあたる約230万社が倒産したと分析しているほどだ。
この対策として、今年の全人代では、人員削減を行わない企業への税制・金融面での支援、高度な技能をもつ人材の育成拠点の増強を打ち出すなど、雇用の維持や新たな雇用創出に懸命となっている。失業者が増えれば、共産党指導部への不満が強まりかねないからだ。
だが、中国の去年1年間の小売業の売上高は前年より3.9%も減少したほか、中国の財政収入もマイナス3.9%と官民とも回復は道半ば。中国の財政収入は前年比11.5兆円のマイナスとなっている。
その一方で、コロナ対策の巨額財政出動が不動産市場で投機的な行動を後押しし、住宅価格が高騰しており、政府の幹部も「バブルの傾向が比較的強い」と警戒感を示しているほどだ。
中国の企業債務残高も急増している。国際決済銀行(BIS)によると、中国の企業債務残高は08年末の31兆元(約480兆円)から18年末の136兆元(約2100兆円)へ4倍超に膨らんだ。企業債務残高の対国内総生産(GDP)比は98%から152%まで上昇し、その債務急膨張の様相はバブル期の日本と類似する。
さらに2020年には、企業は業績不振が続いて借金を膨らませ、その総額はGDPの2倍以上に達している。中国国家統計局が今年2月28日に発表した公式為替レートをもとに計算したドル建てのGDPは前年比3.0%増の14兆7300億ドル(約1550兆円)となっているので、GDPの2倍となると、約3100兆円という巨額な数字となる。中国企業は、まさに借金まみれというほかはない。
このようななか、80社以上の国有企業が借金を返せない、いわゆるデフォルトに陥ったと伝えられている。国有企業の借金は政府が保証するという暗黙の了解があるとみられていただけに、相次ぐデフォルトの動きは、経済界に大きな衝撃を広げている。
日本との関係強化
中国の国内経済が悪化するなか、中国指導部は日本との関係強化を急いでいる。沿海部の大連や青島、天津、上海、蘇州のほか、西部の成都といった全国の6主要都市では、日本企業を誘致するためのモデル地区を建設する動きが進んでいる。最新の技術やノウハウを取り込み、地域の雇用拡大につなげたいとの思惑が見え隠れする。
日本企業も中国の巨大市場は大きな魅力だが、中国に技術が流出する可能性は捨てきれない。とくに軍事転用可能な技術の流出は米国が極めて警戒するところであり、日本企業はおいそれと中国側の誘いに乗れないとの事情もある。
また政治的な問題も多い。中国の巡視船の武器使用などを合法化する「海警法」が全人代の直前に施行されており、日本の沖縄県尖閣諸島周辺で領海侵犯を繰り返す中国の巡視船がますます威嚇的な行動に出てくるとの懸念も出ているなかで、日本企業にとって、対中進出は極めてリスキーな選択といえる。
特に、本稿の冒頭に述べたように、新疆ウイグル自治区の人権問題をめぐって、欧米諸国が相次いで、対中制裁に乗り出しているのに加えて、日本の同盟国の米国と、中国との関係は極めて険悪な状態であり、日本側は当面、極めて慎重な姿勢をとらざるを得ないだろう。
(取材・文=相馬勝/ジャーナリスト)
●相馬勝/ジャーナリスト
1956年、青森県生まれ。東京外国語大学中国学科卒業。産経新聞外信部記者、次長、香港支局長、米ジョージワシントン大学東アジア研究所でフルブライト研究員、米ハーバード大学でニーマン特別ジャーナリズム研究員を経て、2010年6月末で産経新聞社を退社し現在ジャーナリスト。著書は「中国共産党に消された人々」(小学館刊=小学館ノンフィクション大賞優秀賞受賞作品)、「中国軍300万人次の戦争」(講談社)、「ハーバード大学で日本はこう教えられている」(新潮社刊)、「習近平の『反日計画』―中国『機密文書』に記された危険な野望」(小学館刊)など多数。
【私の論評】中国には雇用が劣悪化しても改善できない構造的理由があり、いまのままではいずれ隠蔽できなくなる(゚д゚)!
中国の李克強首相は5日の全国人民代表大会(全人代)の政府活動報告で、新型コロナウイルス感染症対策での「戦略的成果」を取り上げ、2020年の成長率は2・3%と「予想を上回る回復だった」と胸を張りました。この数値は、このブログに以前掲載したように、全くのフェイクです。
 |
| 全人代の会場で大型スクリーンに映し出された李克強首相 |
政府が発表する失業率は、実は都市に戸籍を持つ人が対象で、地方出身者はデータに含まれていません。北京大学国家発展研究院の姚洋院長は20年12月、中国メディアに対し、都市部の出稼ぎ労働者や農村部を含めると、失業率は20%、失業者は1億人以上いるとの試算を明らかにしました。
昨年(2020年)10-12月期の中国のGDPは、前年同期比で6.5%増えたことになっています。2019年の10-12月期といえばコロナ騒動は全くありませんでした。コロナ禍が全くなかったこの時と比べて、途中でコロナ禍で大きく経済が落ち込んだはずなのに、1年後はそんな影響などまるでなかったかのように、6.5%成長していると言っているのです。
中国が発表した昨年(2020年)の四半期ごとのGDP成長率は、前年同期比で1-3月期がマイナス6.8%、4-6月期がプラス3.2%、7-9月期がプラス4.9%、10-12月期がプラス6.5%です。この数字を前期比に変えると、年率換算で1-3月期がマイナス37%、4-6月期がプラス60%、7-9月期がプラス13%、10-12月期がプラス12%です。
1-3月期のマイナス37%は随分大きなマイナスに見えるかもしれないですが、英国の4-6月期のマイナス60%と比べると遥かに軽いことになります。
確かにコロナ禍は英国に大きな打撃を与えました。コロナ禍前のイギリスの完全失業率は4.0%でしたが、コロナ禍発生後に最大で5.1%にまで上昇しました。失業率が1.1%も上昇し、それが一時的にはGDPマイナス60%という大きなブレーキにつながったのです。
中国政府が発表する失業率統計はGDP同様全くあてにならないことで有名であり、これをそのまま真に受けるわけにはいきません。では、他の機関はどのような数値を出しているのみてみます。
アジア開発銀行は6290万人から9520万人が新たに失業したのではないかと推計しました。「スイス銀行」の俗称で知られるUBSは7000万人から8000万人が新たに失業したのではないかと推計しました。中国の有名エコノミスト、李迅雷氏も、新たな失業者は7000万人を超えるとし、これによって失業率が20.5%まで高まったのではないかと述べています。
コロナ禍で失業したりビジネスが立ち行かなくなって困窮した人たちもいるだろうということで、日本では10万円の定額給付金が支給されました。その他にも様様な精度があり、給付金が支給されました。英国でも休業せざるをえなくなった事業者や従業員に対して政府が最大8割の手当を支給しました。
そうして、その対策が奏功して、にほんでは失業率が比較的低い水準で推移しています。これは、昨日このブログにも掲載したばかりです。その時掲載した表を以下に掲載します。中国の統計は中国は先進国でもないし、出鱈目でもあるので掲載しません。
ところが、中国ではこうした痛み止めの支給は行われていません。失業率が10%も増え、経済的に苦しくなった国民に対する痛み止めの支給もなかったにもかかわらず、経済へのダメージは英国よりもはるかに軽く済んだということなどあり得ません。
政府による経済対策は、他の指標が悪くても少なくとも雇用が悪化しなければ、合格といわてています。その点では、日本政府は上のグラフからみてもわかる通り、優等生といえます。
中国は1-3月期にマイナス37%の大きな落ち込みがあった後の4-6月期にプラス60%にも及ぶ超V字回復を果たしたことになっています。ではこの超V字回復を果たした後の6月末の失業率はどの程度だったのでしょう。
北京大学国家発展研究院の姚洋所長の推計によれば、6月末での完全失業率は15%で、時々アルバイト的なことをやることはあってもほぼ失業しているのと同然の「半失業」の人たちを加えると、失業率は20%になるとしました。これでは、中国政府は雇用の劣等生ということになります。雇用がだめということは、経済対策が駄目ということです。
コロナ禍で1-3月に大きく落ち込んだ経済が4-6月期に超V字回復を果たしたはずなのに、失業率の改善は大して見られないのです。こうなるとこの超V字回復自体が怪しいです。
中国の中国はどうしてこれほどまで悪化しているのに、習近平政権はこれを本格的に修復しようとしないのでしょうか。これは、以前このブログでも述べたように、中国は国際金融のトリレンマという罠にはまり込んでいるからです。その記事のリンクを以下に掲載します。
中国・李首相が「バラマキ型量的緩和」を控える発言、その本当の意味―【私の論評】中国が金融緩和できないのは、投資効率を低下させている国有ゾンビ企業のせい(゚д゚)!
この記事は、2019年3月31日のものです。詳細はこの記事をご覧いただくものとして、以下に一部を引用します。
先進国が採用するマクロ経済政策の基本モデルとして、マンデルフレミング理論というものがある。これはざっくり言うと、変動相場制では金融政策、固定相場制では財政政策を優先するほうが効果的だという理論だ。
この理論の発展として、国際金融のトリレンマという命題がある。これも簡単に言うと(1)自由な資本移動、(2)固定相場制、(3)独立した金融政策のすべてを実行することはできず、このうちせいぜい2つしか選べない、というものだ。
先進国の経済において、(1)は不可欠である。したがって(2)固定相場制を放棄した日本や米国のようなモデル、圏内では統一通貨を使用するユーロ圏のようなモデルの2択となる。もっとも、ユーロ圏は対外的に変動相場制であるが。
共産党独裁体制の中国は、完全に自由な資本移動を認めることはできない。外資は中国国内に完全な自己資本の民間会社を持てない。中国へ出資しても、政府の息のかかった国内企業との合弁経営までで、外資が会社の支配権を持つことはない。
ただ、世界第2位の経済大国へと成長した現在、自由な資本移動も他国から求められ、実質的に3兎を追うような形になっている。現時点で変動相場制は導入されていないので、結果的に独立した金融政策が行えなくなってきているのだ。
一昔前の中国なら、雇用が悪化すればすぐに金融緩和したでしょうが、2019年時点でそれができない状態になっているのです。ちなみに、金融緩和すれば雇用が良くなるというのは、日本ではまるで非常識のように捉えられる場合もありますが、これは世界では経済学上の常識です。
これでは、雇用が悪化しても金融緩和できず、中国はこれから向上的に失業率が悪化し続ける可能性が大きいです。
このブログにも以前から掲載しているように、中国の経済統計がおかしいのは2020年だけではありません。随分前からそうです。
中国のスマホの国内出荷台数は2016年に5.6億台だったのが、2017年に4.9億台、2018年に4.1億台、2019年に3.9億台、2020年に3.1億台と、年々縮小し続けています。スマホは2〜3年もすればバッテリーのもちが悪くなって買い替えたくなるものだが、買い替え需要があまり発生していません。スマホは中国でも、多くの人の必需品になったようですが、それにしても横ばいではなく、年々下がっているのです。
中国の乗用車の販売台数の推移はどうかといえば、2017年に2376万台だったのが、2018年に2235万台、2019年に2070万台、2020年に1929万台と、やはり年々落ちています。これを見ると富裕層の消費も伸びているとは考えにくいです。
これでは、毎年6%以上の経済成長を続けてきたという話自体がフェイクだと考えないと辻褄が合わないです。
習近平は改革・開放と民営化によって伸びてきた中国経済を、社会主義的統制を強化することでどんどんと潰しています。例えばアリババなどのIT企業がさらに伸びれば、ITによる世界支配に貢献できるであろうに、習近平は愚かにもこうしたIT企業を解体・弱体化する方向に舵を切りました。
習近平独裁体制が強化される中で、習近平のやることに誰も異論を挟むことができなくなり、経済の崩壊速度が高まっています。そうしてこの現実を覆い隠すために、経済統計のフェイクのレベルが以前よりも強化されていると見るのが、正しい中国経済の見方でしょう。
中国経済は「世界一の人口を抱えて世界一のマーケットになる潜在力がある」「中国経済はまだまだこれからだ」といった幻想によって支えられているにすぎません。
日本企業は中国幻想など捨てて、等身大の中国経済を知ることによって、今のうちに思い切った撤退を進めるべきです。早ければ早いほど、傷口は小さくすむでしょう。中国に進出するには、現在の中共が崩壊して、民主化、経済と政治の分離、法治国家化がなされた後にすべきです。
中国幻想に酔っている方々、すぐに酔いを冷ましたほうが良いです。
【関連記事】
米中「新冷戦」が始まった…孤立した中国が「やがて没落する」と言える理由―【私の論評】中国政府の発表する昨年のGDP2.3%成長はファンタジー、絶対に信じてはならない(゚д゚)!